本文
個別労働関係紛争あっせん事例集
目次
| 目 次 | |
|---|---|
| 1 解雇 | (1)解雇撤回 |
| (2)解雇撤回 | |
| 2 退職強要 | (1)自己都合(退職強要)から会社都合退職へ |
| 3 懲戒 | (1)懲戒解雇 |
| 4 配置転換 | (1)配置転換 |
| 5 賃金未払 | (1)賃金未払 |
| 6 降格 | (1)降格処分 |
| 7 労働条件 | (1)労働条件の不利益変更 |
| 8 その他 | (1)過重な労働による心の病 |
| (2)パワーハラスメント | |
| (3)パワーハラスメント | |
1 解雇
(1)解雇撤回
労働者の主張
|
使用者の主張
|
●あっせんでは・・・
使用者には、労働者が同業他社を紹介したことをもって懲戒解雇としたことは懲戒解雇権の濫用にあたる可能性があることを伝え、労働者には、会社のルールを乱すことで会社が損失を被ることを説明し、譲歩を促しました。
○あっせん結果
解雇撤回の合意はできなかったが、懲戒解雇を普通解雇に変更し、労働者に解決金を支払うことで双方が合意し、解決しました。
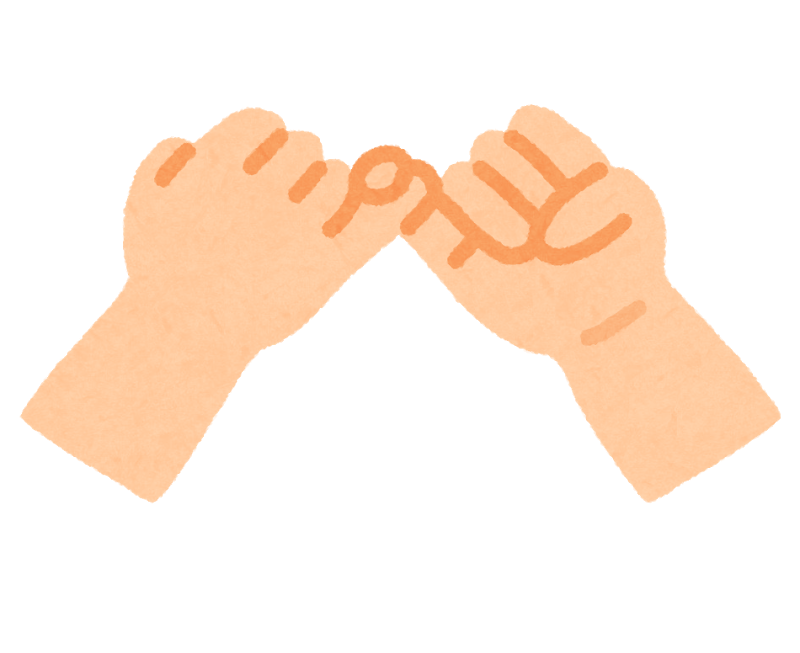
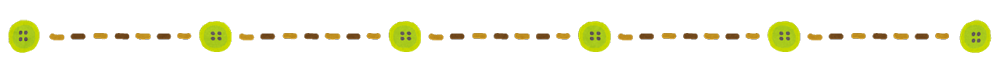
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
懲戒が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります(労働契約法第15条)。
解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります(労働契約法第16条)。
 こんな判例があります
こんな判例があります
使用者が懲戒解雇事由にあたると考えた事実を懲戒解雇事由にあたるとは評価しえない場合でも、普通解雇としての効力が生じないかどうかを検討する必要があるとして転換可能性を認めた判例(日本経済新聞社事件東京地判昭45.6.23)
(2)解雇撤回
労働者の主張 正社員として20年以上同じ職場で事務の仕事を続けてきたが、パート社員への変更を告げられた。拒否したところ、能力不足だとして、即日解雇された。不当解雇であり撤回してほしい。 正社員として20年以上同じ職場で事務の仕事を続けてきたが、パート社員への変更を告げられた。拒否したところ、能力不足だとして、即日解雇された。不当解雇であり撤回してほしい。 |
使用者の主張 幹部候補として採用したが、労働者は能力が低く、補助的な業務しかできなかったことから、パート社員への変更を打診したところ拒否されたため、就業規則に基づき解雇した。労働者を配置する部署がないため、解雇撤回はありえない。 幹部候補として採用したが、労働者は能力が低く、補助的な業務しかできなかったことから、パート社員への変更を打診したところ拒否されたため、就業規則に基づき解雇した。労働者を配置する部署がないため、解雇撤回はありえない。 |
●あっせんでは・・・
使用者には、長年にわたり、同様の仕事をさせていながら、適切な指導を行わず、急に能力不足で解雇することは困難であることを指摘し、労働者には、仕事内容と賃金がアンバランスであることを示し、双方が譲歩できる点を探りました。
○あっせん結果
労働者が解雇の撤回を強く主張したものの、使用者はこれまでの労働条件での雇用に難色を示したため、労働条件を一部引き下げた上での復職で労使双方に譲歩を促したところ、合意が成立し、解決しました。

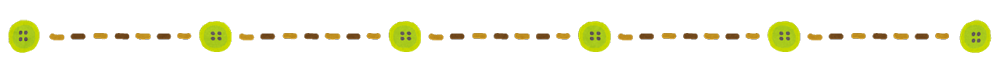
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
労働者と使用者は、合意により労働条件を変更することができます。(労働契約法8条)
解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。(労働契約法16条)
 こんな判例があります
こんな判例があります
長期間勤務の実績がある場合、解雇に当たって、単なる成績不良ではなく、企業経営に支障・損害を生じ又は重大な損害を生じる恐れがあることを要し、是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、改善されないなど今後の改善の見込みもないことなども考慮して濫用の有無を判断すべきとして、解雇を無効とした判例(エース損害保険事件東京地決平13.8.10)
労働者の能力等に重大な問題があり、使用者が教育訓練や配置転換等による解雇回避の努力をしてもなお雇用の維持が困難である場合に、解雇は有効であるとした判例(三井リース事業事件東京地決平6.11.10)
2 退職強要
(1)自己都合(退職強要)から会社都合退職へ
労働者の主張 パート職員として勤務していたが、会社の物品を私的に利用したとして退職願を書かされた。自分だけが退職強要を受けており、慰謝料を求める。 パート職員として勤務していたが、会社の物品を私的に利用したとして退職願を書かされた。自分だけが退職強要を受けており、慰謝料を求める。 |
使用者の主張 労働者に対して聴き取り調査をしたところ違反行為を認め、その場で労働者が退職を願い出た。退職願は労働者が任意で記載したものであり強要したものではない。 労働者に対して聴き取り調査をしたところ違反行為を認め、その場で労働者が退職を願い出た。退職願は労働者が任意で記載したものであり強要したものではない。 |
●あっせんでは・・・
あっせん員が確認したところ、退職願が、使用者が文面を記載して準備したものであったことから、退職強要と取られかねないものであるとして使用者に大幅な譲歩を促すとともに、労働者には、会社の物品の私的利用は就業規則違反と認められるため、金額について譲歩を促しました。
○あっせん結果
離職票の退職理由欄を自己都合退職から会社都合退職に変更するとともに、使用者が謝罪し、解決金を支払うことで双方が合意し、解決しました。
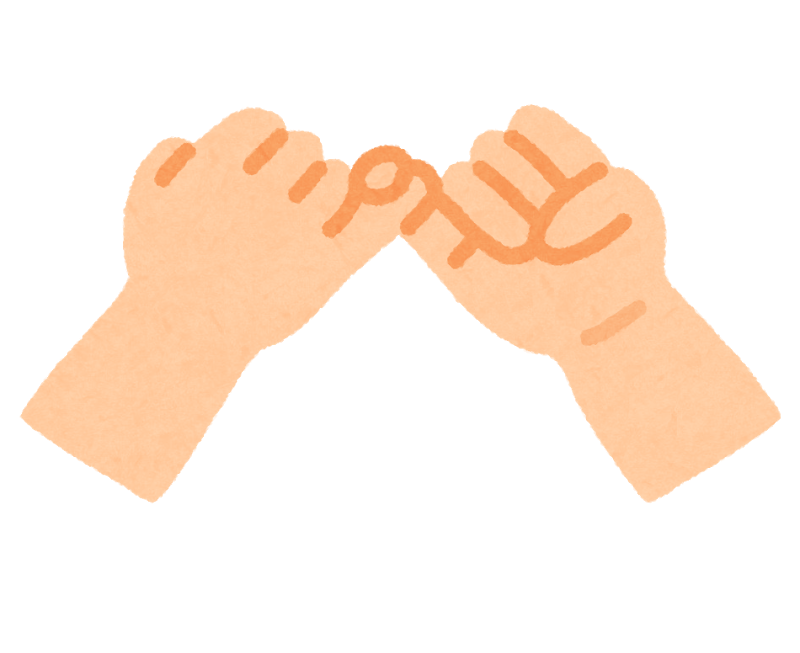
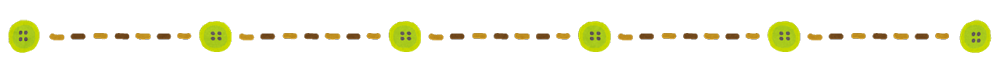
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
企業秩序を維持するため、通常の企業では、懲戒解雇、諭旨解雇、戒告などとして、懲戒の基準を制度化していることが一般的です。
 こんな判例があります
こんな判例があります
事務所経費で飲食したことについて、退職しなければ告訴も考えていると言われた労働者が退職届を提出した事案について、退職届は取り消しうるとした判例(ニシムラ事件大阪地決昭61.10.17)
正常な判断能力を失い、退職願を提出するにいたったものとは認められないとした判例(ネスレジャパンホールディングス事件東京高判平13.9.12)や退職の意思表示につき、強迫等は認められず、合意解約が成立しているとされた判例(大阪屋事件大阪地判平3.8.20)
繰り返してなされる、執拗で、半強制的な退職の勧めは不法行為となるとした判例(下関商業高校事件最判昭55.7.10)
3 懲戒
(1)懲戒解雇
労働者の主張 何者かが自分の個人情報を収集して会社中に流している。同僚から当該情報を基にした嫌がらせを受けているため、会社に事実を調査するよう依頼したが無視された。そこで本件が解決するまで休職を申し出たが認められなかったので、有給休暇をすべて取得した後、約30日間欠勤したら、無断欠勤を理由に懲戒解雇とする通知を受けた。この処分は無効であるので撤回を求める。 何者かが自分の個人情報を収集して会社中に流している。同僚から当該情報を基にした嫌がらせを受けているため、会社に事実を調査するよう依頼したが無視された。そこで本件が解決するまで休職を申し出たが認められなかったので、有給休暇をすべて取得した後、約30日間欠勤したら、無断欠勤を理由に懲戒解雇とする通知を受けた。この処分は無効であるので撤回を求める。 |
使用者の主張 労働者が主張する被害事実は存在しないので、就業規則所定の懲戒事由である「正当な理由なしに無断欠勤が引き続き14日以上に及ぶとき」に該当する。この処分は有効であり、撤回するつもりはない。 労働者が主張する被害事実は存在しないので、就業規則所定の懲戒事由である「正当な理由なしに無断欠勤が引き続き14日以上に及ぶとき」に該当する。この処分は有効であり、撤回するつもりはない。 |
●あっせんでは・・・
本件欠勤が労働者の精神的な不調に基づくものであり、使用者はその疑いを抱くことができたこと、健康診断の実施や診断結果に応じた治療の勧め、休職等の処分の検討等を経ずに直ちに懲戒処分を行ったことは適切な対応ではなかったこと等を使用者に説明し、譲歩を促しました。
○あっせん結果
使用者は懲戒解雇を撤回し、精神科医による健康診断を実施した上で、その診断結果等に応じて休職等の処分を検討することで双方が合意し、解決しました。
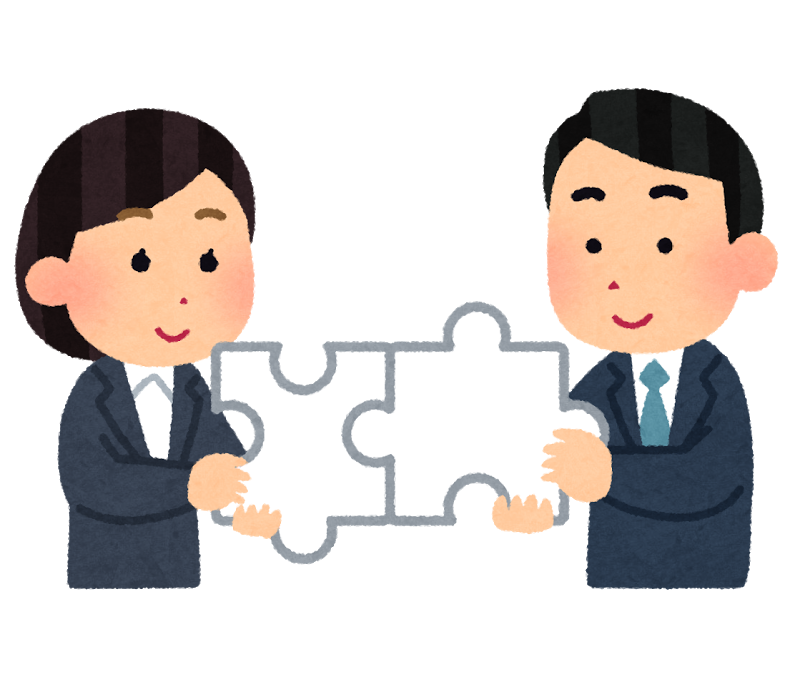
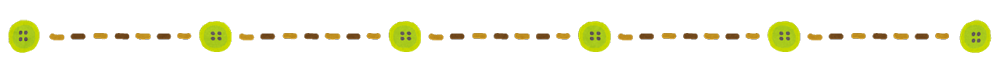
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする必要があります(労働契約法第5条)。
懲戒が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります(労働契約法第15条)。
 こんな判例があります
こんな判例があります
住居侵入罪で処罰された労働者(被上告人)を懲戒解雇したことについて、被上告人の行為が、上告会社の体面を著しく汚したとまで評価するのは当たらないとして、解雇を無効とした判例(横浜ゴム事件最判昭45.7.28)
逮捕拘留されたことによる無断欠勤、経歴詐称、禁固以上の刑に処せられたこと、構内でのビラ配りを理由として労働者を懲戒解雇したことについて、懲戒解雇を有効とした判例(炭研精工事件 最判平3.9.19)
4 配置転換
(1)配置転換
労働者の主張 うつ病となり休職していたが、復職することとなった。しかし、元の職場への復帰が認めてもらえず、別の職場の補助作業をすることとなった。給料も下がり、職場にも慣れないため、元の職場に戻してほしい。 うつ病となり休職していたが、復職することとなった。しかし、元の職場への復帰が認めてもらえず、別の職場の補助作業をすることとなった。給料も下がり、職場にも慣れないため、元の職場に戻してほしい。 |
使用者の主張 職場復帰は認めたが、今の労働者の健康状態では大型の機械を扱う元の職場での勤務は危険だと思われるため、まずは補助作業として復帰させた。今後の労働者の状態次第で、元の職場に戻ることも給料が上がることもありえる。 職場復帰は認めたが、今の労働者の健康状態では大型の機械を扱う元の職場での勤務は危険だと思われるため、まずは補助作業として復帰させた。今後の労働者の状態次第で、元の職場に戻ることも給料が上がることもありえる。 |
●あっせんでは・・・
使用者には、元の職場に復帰できるまでの道筋等を労働者に明示するように、労働者には、第三者から見ても、現状では安全配慮のため必要な措置であることを理解するよう促しました。
○あっせん結果
労働者の健康状態に配慮し、職場配属、処遇等について十分話し合うということで双方が合意し、解決しました。

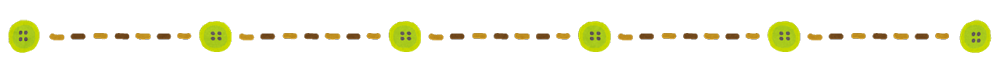
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすることとされています。(労働契約法5条)
 こんな判例があります
こんな判例があります
治癒したものの、従前の職務を遂行する程度に回復していない場合は、復職が認められないとした判例(アロマカラー事件東京地決昭54.3.27)
当初は軽業務に就業させれば、その後通常業務への復帰が可能である場合、使用者に配慮を行うことを義務付けた判例(エール・フランス事件東京地判昭59.1.27ほか)
5 賃金未払
(1)賃金未払
労働者の主張 突然社長から、給料の支払ができないから辞めてほしいと言われた。今月の給料の支払について聞くと、仕事中に傷つけた社有車の修理代と相殺すると言われた。仕事中の事故なので修理代は払いたくない。 突然社長から、給料の支払ができないから辞めてほしいと言われた。今月の給料の支払について聞くと、仕事中に傷つけた社有車の修理代と相殺すると言われた。仕事中の事故なので修理代は払いたくない。 |
使用者の主張 労働者には、これ以上営業成績が悪かったら解雇すると言ってあった。未払いの給料は支払うつもりだが資金がない。車は労働者が入社したときに新車の営業車を貸し与えたものなので、返す時は貸した時の状態にして返すべきである。 労働者には、これ以上営業成績が悪かったら解雇すると言ってあった。未払いの給料は支払うつもりだが資金がない。車は労働者が入社したときに新車の営業車を貸し与えたものなので、返す時は貸した時の状態にして返すべきである。 |
●あっせんでは・・・
使用者には、使用者の指揮命令下の労働により使用者が経済的利益を得ていることから、故意や重過失がない限り、裁判で損害賠償が認められる可能性は低いことを説明し、譲歩を促しました。
労働者には、使用者の経営状況を説明し、給料支払の猶予を促しました。
○あっせん結果
未払い分の賃金を含む解決金を使用者が労働者に分割して支払うことで双方が合意し、解決しました。
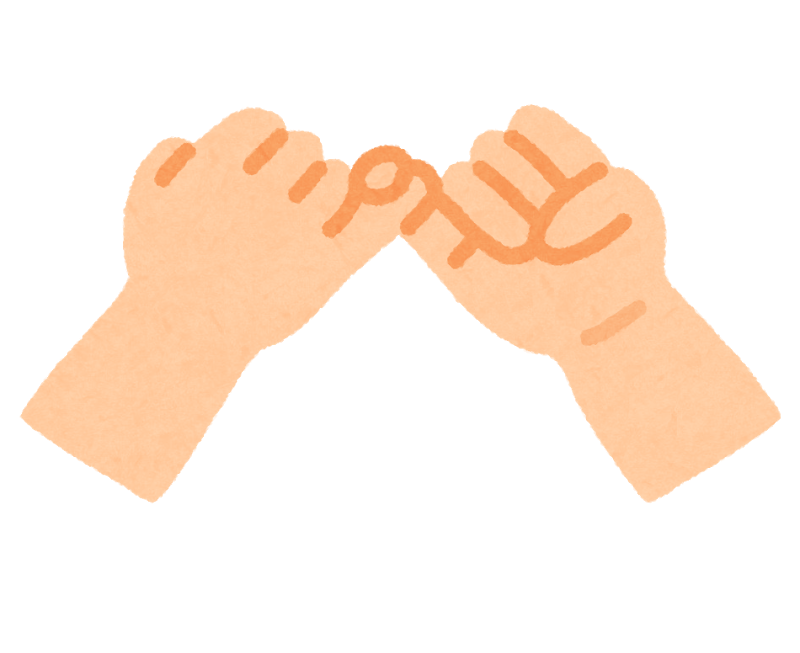
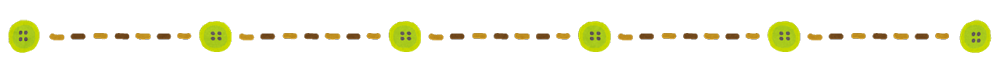
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
労働者が労働義務や付随的義務に反して使用者に損害を与えた場合、労働者は使用者に対し、その損害を賠償しなければなりません(民法第415条、同第416条)。
しかしながら、労働者に過酷であるため、裁判例では損害の公平な分担という見地から、労働者の損害賠償責任が軽減されています。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません(労働基準法第24条)。
 こんな判例があります
こんな判例があります
タンクローリーの運転中の交通事故で、使用者が保険未加入であり、労働者の勤務成績が普通以上だったことから、労働者の負担は全損害の4分の1を限度とした判例(茨城石炭商事事件 最判昭51.7.8)
夜勤中の居眠りで工作機械に損傷を与えた事故で、労働者の過失は重大であるとしつつも、使用者と従業員の経済力、賠償の負担能力の格差や使用者が機械保険に加入するなどの損害軽減措置を講じていなかったことから、労働者の負担を損害額の4分の1とした判例(大隈鉄工所事件 名古屋地判昭62.7.27)
労働者に対する損害賠償請求を賃金と相殺することは、全額払いの原則に反して許されないとする判例(関西精機事件最判昭31.11.2、日本勧業経済会事件 最判昭36.5.31)
6 降格
(1)降格処分
労働者の主張 営業部長職として採用され勤務していたが、取引先での評判が悪い、仕事ができないという理由で、部長職を解かれ、一担当社員に降格となった。降格人事の撤回を求める。 営業部長職として採用され勤務していたが、取引先での評判が悪い、仕事ができないという理由で、部長職を解かれ、一担当社員に降格となった。降格人事の撤回を求める。 |
使用者の主張 降格は就業規則に定められており、降格にあたっては、労働者に対して役員全員で聞き取りを行った。正当な人事評価の上での決定事項なので撤回することはできない。 降格は就業規則に定められており、降格にあたっては、労働者に対して役員全員で聞き取りを行った。正当な人事評価の上での決定事項なので撤回することはできない。 |
●あっせんでは・・・
あっせん員が双方の意見を聴取し、使用者には、降格人事の相当性につき人事権濫用となった裁判例を説明して譲歩を促すとともに、労働者にも労働条件面で譲歩できることがないかを探りました。
○あっせん結果
降格人事を撤回して営業部長職に留めることとし、次回の人事評価において、それまでの勤務成績等を基に労働契約内容の変更等の検討をすることで双方が合意し、解決しました。
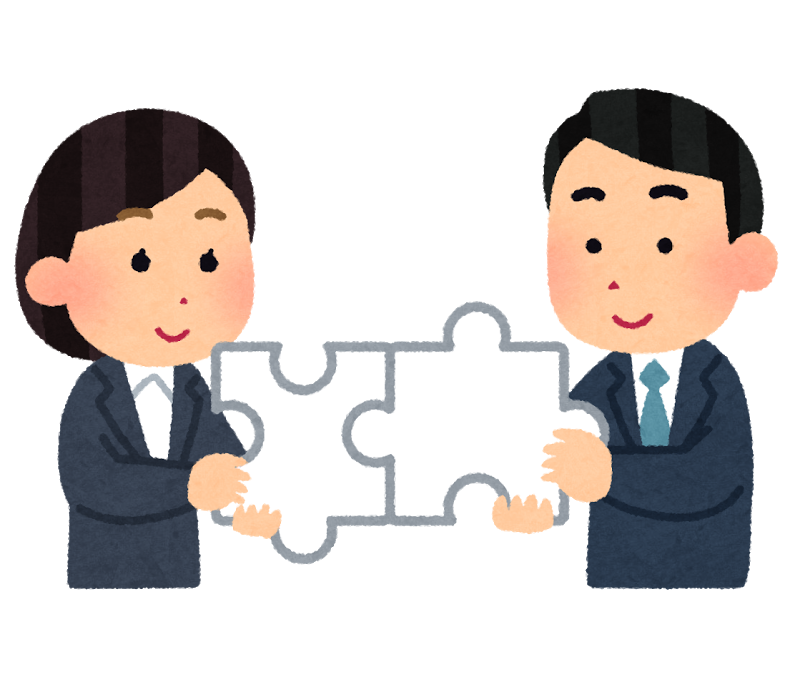
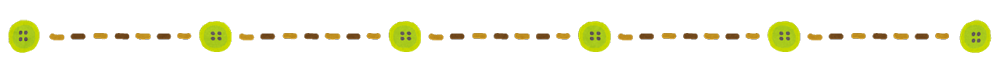
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされています。(労働契約法第8条)
 こんな判例があります。
こんな判例があります。
職種が一定レベルのものに限定された労働者を不適格性を理由に低いレベルのものに引き下げる降格は、一方的措置としてはなしえないとした判例(デイエフアイ西友事件東京地判平9.1.24)
7 労働条件
(1)労働条件の不利益変更
労働者の主張 会社の業績悪化によって退職を選択した。しかし、十分な説明を受けずに退職する数ヶ月前から賃金を減額されていた。賃金差額分の支払を求める。 会社の業績悪化によって退職を選択した。しかし、十分な説明を受けずに退職する数ヶ月前から賃金を減額されていた。賃金差額分の支払を求める。 |
使用者の主張 業績悪化が深刻化したため、賃金を減額せざるをえなくなった。在職中から賃金減額について知っていたはずであり、異議を唱えられたことはない。 業績悪化が深刻化したため、賃金を減額せざるをえなくなった。在職中から賃金減額について知っていたはずであり、異議を唱えられたことはない。 |
●あっせんでは・・・
使用者には、賃金減額の理由について労働者に十分に説明して合意を得る必要があること、また、判例からみて、労働者から特段の異論や反対がないからといって労働者との合意が確定的に成立したとは認められにくいことを指摘し、労働者には、会社は業績悪化によって資金繰りが困難であるため、分割払いでの賃金差額分支払を提案し、双方に譲歩を促しました。
○あっせん結果
使用者が賃金差額分を分割払いで支払うことで双方が合意し、解決に至りました。

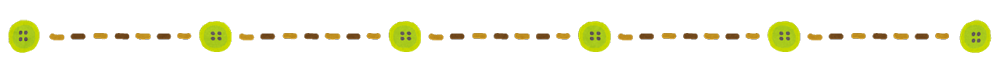
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
労働条件は、労働者及び使用者の合意によって変更することができるとされています(労働契約法第8条)。
 こんな判例があります。
こんな判例があります。
労働者が賃金減額について承諾したと認めることはできず、使用者が一方的に賃金を減額することは許されないとした判例(更生会社三井埠頭事件東京高判平12.12.27)
労働者が賃金体系の変更について異議を述べなかったことから黙示の合意が認められた判例(エイバック事件東京地判平11.1.19)
※判例の多くでは、黙示の合意の認定は慎重に行われています。
8 その他
(1)過重な労働による心の病
労働者の主張 激務で過重な責任を負わされ、精神疾患を発症し、結果的に退職せざるを得なくなった。 激務で過重な責任を負わされ、精神疾患を発症し、結果的に退職せざるを得なくなった。 |
使用者の主張 激務ではなく、他の従業員と同程度の勤務であるため、精神疾患の発症は勤務が原因ではないと考える。退職は労働者が自ら選んだことである。 激務ではなく、他の従業員と同程度の勤務であるため、精神疾患の発症は勤務が原因ではないと考える。退職は労働者が自ら選んだことである。 |
●あっせんでは・・・
労働環境及び規則の不備があり、使用者の譲歩を促すとともに、労働者の主張を傾聴したうえで、譲歩を促しました。
○あっせん結果
会社都合による退職とし、使用者が解決金を支払うことで双方が合意し、解決しました。
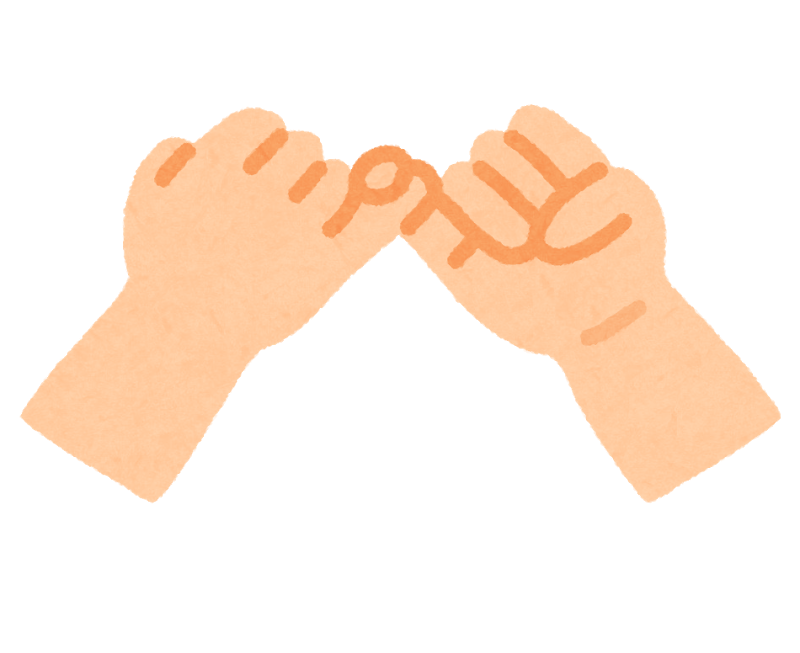
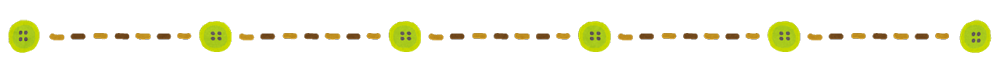
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする必要があります(労働契約法第5条)。
 こんな判例があります
こんな判例があります
使用者は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとした判例(電通事件最判平12.3.24)
(2)パワーハラスメント
労働者の主張 上司から毎日のように仕事や仕事以外の細かいことで理不尽な叱責、嫌がらせを受けた。耐え切れずに退職したが、このことが原因で体調を崩し、病院に通院している。精神的苦痛に対する慰謝料と治療費の支払を求める。 上司から毎日のように仕事や仕事以外の細かいことで理不尽な叱責、嫌がらせを受けた。耐え切れずに退職したが、このことが原因で体調を崩し、病院に通院している。精神的苦痛に対する慰謝料と治療費の支払を求める。 |
使用者の主張 仕事を遂行する上で必要な注意、指導を行ったが、労働者は自己主張が強く、改善されることはなかった。金銭要求に応じる理由はない。 仕事を遂行する上で必要な注意、指導を行ったが、労働者は自己主張が強く、改善されることはなかった。金銭要求に応じる理由はない。 |
●あっせんでは・・・
あっせん員が紛争の長期化による費用負担の増加等の懸念を説明し、あっせんでの早期解決を勧め、労使相互の譲歩を促しました。
○あっせん結果
使用者が金銭による解決を受け入れ、解決しました。

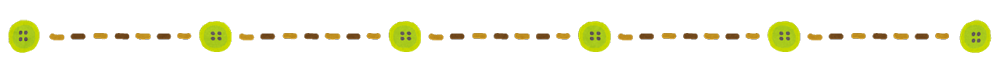
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる1.優越的な関係を背景とした言動であって、2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3.労働者の就業環境が害されるものであり、1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます(労働施策総合推進法第30条の2)。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすることとされています(労働契約法5条)。
 こんな判例があります
こんな判例があります
叱咤激励が限度を超えており不法行為責任を認めた判例(A保険会社上司事件東京高判平17.4.20)
厳しい指導が業務上の指示の範囲内であるとした判例(医療法人財団健和会事件 東京地判平21.10.15)
(3)パワーハラスメント
労働者の主張
|
使用者の主張 労働者は勤務態度が著しく不良であったため、注意や指導を行った。パワーハラスメントの事実はないと認識している。 労働者は勤務態度が著しく不良であったため、注意や指導を行った。パワーハラスメントの事実はないと認識している。 |
●あっせんでは・・・
使用者には、業務上適正な範囲を超える注意・指導はパワーハラスメントと捉えられかねないこと、職場のパワーハラスメントを予防・解決するための対策が必要であることを説明し、労働者には、職務上の義務に違反した行為(職務怠慢、無断欠勤等)は就業規則に基づいた処分を受けかねないことを指摘し、譲歩を促しました。
○あっせん結果
使用者は、自社の従業員に対してパワーハラスメント防止について周知・啓発を行う等、その防止に努めること、労働者は、就業規則に基づく服務規律を遵守することで、双方が合意しました。
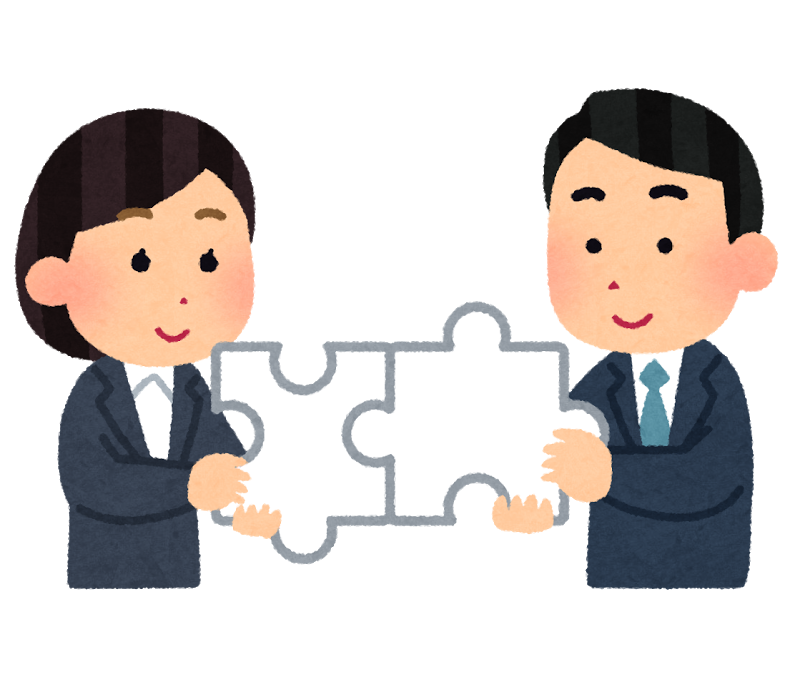
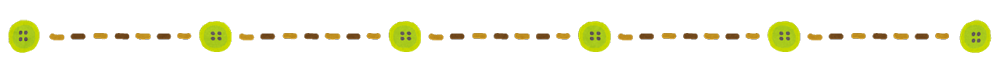
 労働法まめ知識
労働法まめ知識
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる1.優越的な関係を背景とした言動であって、2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3.労働者の就業環境が害されるものであり、1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます(労働施策総合推進法第30条の2)。
使用者は、職場におけるパワーハラスメント防止のため、一定の措置を講じることが義務付けられています(労働施策総合推進法第30条の3第2項)。
使用者は、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとされています(労働契約法第5条)。
「労働者の生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるとされています。
 こんな判例があります
こんな判例があります
上司のパワハラが安全配慮義務に違反すると同時に不法行為を構成すると認められた判例(日本土建事件津地判平21.2.19)
労働者の主張には理由がないとしてパワハラが認められなかった判例(ホンダカーズA株式会社事件大阪地判平25.12.10)
なお、他の事例については、中央労働委員会のホームページを参考にしてください。

