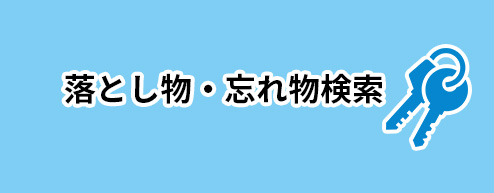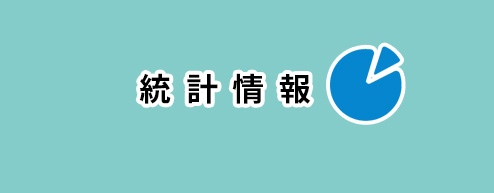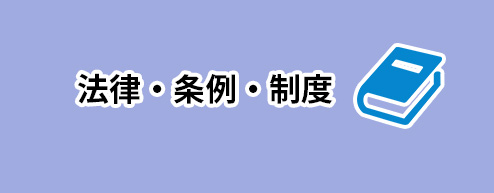#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
悪質商法の被害に遭わないために!
~最近の相談・被害事例と対応方法~

悪質な訪問販売業者に注意!
・近所で工事をしているという業者が来訪して「水道管の工事が必要」と契約を勧めてきた。→でも近所で工事をしているところは見当たらない。
・無料で点検するという業者が来訪して、屋根に登って「瓦がずれている」と修理を勧めてきた。→後日専門家に屋根を確認してもらったところ修理の必要がないことがわかった。
これらは悪質な訪問販売業者の手口の一例です。
悪質業者は突然来訪して「工事をしないと危険」等と不安をあおったり「今なら安く工事できる」等と言って契約を迫ってきます。
ここで大切なことは、
慌てて契約書にサインしたり現金を渡したりしないこと
です。説明を全て理解して、納得してから契約するようにしましょう。
もし望まない契約をしてしまったとしても、クーリング・オフによって契約解除できる場合もあります。
また、関東地方で相次いでいる強盗事件で被害に遭った住宅は、事前にリフォーム業者が訪問して把握した資産等の個人情報が悪用された可能性があるとも言われています。
身分を明かさない、断っても長時間居座る、リフォームと関係ないことについて聞いてくるといった不審な業者がいましたら、110番または最寄りの警察署に通報してください。
ここでは悪質な訪問販売業者に対応するための「特定商取引に関する法律」や最近の相談事例を紹介します。
〇特定商取引に関する法律
この法律は、業者の悪質な勧誘行為等を防止して消費者の利益を守ることを目的にしています。
① 訪問販売における氏名等の明示
訪問販売業者は、勧誘開始前に、業者名、氏名、勧誘目的であること、商品またはサービスの内容を相手に伝えなければいけません。
② 不当な勧誘行為の禁止
根拠もなく公的機関の認定を受けているかのような説明をしたり、事実が無いのに「屋根が壊れていて雨漏りしている」と言うような行為(不実の告知)や「契約しろ」と大声で言われて怖い思いをしたり、「契約しないならここに住めないようにする」と不安になるようなことを言う行為(威迫・困惑)を禁止しています。
③ 書面交付義務
訪問販売で契約を締結した時等に、業者は必要事項が記載された書面を交付する義務があります。
④ クーリング・オフ
クーリング・オフとは、申込みや契約をした後で、書面を受け取ってから一定の期間(訪問販売については8日)内に無条件で解約できる制度です。
1 点検商法
点検商法とは、高齢者宅等を訪れ、「瓦がずれているようだから見てあげる。」、「水道水を点検している。」、「布団にダニがいるかもしれない。」など点検等を口実に個人情報を聞き出したり、「早く工事をしないと雨漏りがして柱が腐ってしまう。」、「このような水を飲んでいては体に悪い。」、「病気になるかもしれない。」などと不安をあおり、不要な工事や商品を高額で契約させる商法です。
対象商品(役務)は、住宅リフォーム(屋根瓦、床下乾燥機等)関連のほか、水道管の高圧洗浄、布団の打ち直しなどといった事例が多く見受けられます。
対応方法について
不要なものは、はっきりと断ることが大切ですが、よく分からないときは、自分一人で判断せず、その場で契約しないようにしましょう。
「家族と相談してから決める」、「知り合いの業者と相談する」などと答えることが被害防止になります。
契約書などの書類を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能です。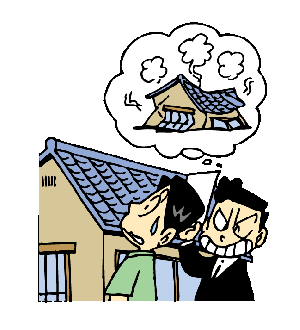
2 訪問買取り(訪問購入)
訪問買取り(訪問購入)の相談事例
自宅にいたら、「ご近所で貴金属の買取り依頼がありましたので、ついでに、この地区を訪問しています。」、「ご不要なものありませんか。」と若い男性2人が訪れました。
私は、「うちには、買い取ってもらえるものなんかありませんよ。」と答えたのですが、男性らは、「何でも、いいんですよ。」「私たちが見てあげますよ。」と、ずかずかと勝手に家に入り込んできました。
そして、居間に座り込み、「古い指輪やネックレスがあるでしょ。」とすごむので怖くなって、早く帰ってもらいたい一心で、使っていない指輪を出そうとタンスの引き出しを開けると、男の一人が私の後ろから、勝手にタンスを開け始め、ネックレス2本と指輪1個を見つけると、「あるじゃない。」「これ、買い取るよ。」と一方的に契約書と2万円を置いて帰っていきました。
持っていかれたのは、昔、十数万円で購入し、大切にしていたものです。取り返すことはできませんか。
訪問購入とは?
物品の購入を業として営むものが、営業所以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入を行うことを言います。
訪問購入については事業者の「飛び込み勧誘」を禁止しています。(不招請勧誘の禁止)
事業者は事前に電話をする等して同意を得てから訪問しなければいけません。
また相手が契約する意思がない事を示した時は、引き続き勧誘することやその後改めて訪問して勧誘することを禁止しています。(再勧誘の禁止)
対応方法について
事例のような買取業者に対しては、
- 曖昧な返事はしない
- どこの業者の誰なのか、はっきり聞く
- 不用意に貴金属類を見せない
- 自宅に上がらせないよう注意する
クーリング・オフの期間(8日間)は、物品を渡さないことが被害防止に有効です。
また、クーリング・オフの期間内であれば、業者が持っていってしまった物品でも返還を求めることができます。
断ったにもかかわらず居座る場合には、110番通報してください。

過去の相談事例
相談1
自宅に、「ご注文いただいた『健康食品』を送りました。」、「代金は〇〇〇〇円になります。」などと電話が入り、家族が頼んだものだと思って、代金引換でお金を払って受け取ってしまいましたが、家族に聞いても誰も注文していないことが分かったので、業者に電話をかけて返金してもらおうと思ったが、「担当が不在。」、「確認後連絡する。」と答えるばかりで返金に応じてもらえない。
身に覚えのない商品は受け取らないことが肝心です。通信販売で商品を購入した場合には、必ずご家族に話をしておくなど、ご家庭での決まり事を作っておくことが被害防止に有効です。
注文していない場合には、代金を支払う必要も自ら商品を送り返す必要もなく、直ちに処分することができます。
対象商品は健康食品のほか、生鮮魚介類などが目立ち、泣き寝入りしやすい数千円から3万円くらいの商品が送られてくる事例が見受けられます。
相談2
会社の工場に消火器点検保守の取引業者を装った業者が訪れ、居合わせた従業員に契約書面であることを伏せてサインさせ、責任者が了解していないのに消火器の薬剤の詰め替え作業を行って、高額な料金を請求された。
一般消費者と違い、事業者は特定商取引に関する法律で定められているクーリング・オフ制度の適用がないため、悪質な消火器点検業者は、会社、工場、学校、幼稚園、病院、スーパー、会社の寮などを専門に狙っています。
被害に遭わないためには、
- 従業員への周知徹底(特に、守衛、窓口)
- 防火管理者などの責任者が対応する
- 勝手に作業させない
- 納得いくまでサイン(押印)しない
- 消防設備士の資格の確認をする
などに心掛けてください。
相談3
学生時代の友人から連絡があり、久しぶりに会いました。すると、友人は「化粧品を友人に紹介するだけでマージンが貰え儲かる。」「いいお小遣いになる。」と話し、しつこく誘うので、根負けして、会員登録した後に20万円の化粧品セットをクレジットカード払いで買いました。その友人は、「20万円なんてすぐ稼げる。」と話しましたが、なかなか買ってくれる人を見付けられず、今後のクレジット返済が心配です。
これは、商品やサービスを契約して、次は自分がお客を探し、契約が取れるとマージンが入るマルチ商法と称される連鎖販売取引で、商売の素人である購入者が次の購入者を探して契約するため、トラブルが多いことが特徴です。
この商法も、特定商取引に関する法律でクーリング・オフが規定されており、契約書面を受領した日、又は商品を受け取った日から20日間は、無償で解約ができます。
友人などの身近な人からの誘いを断るのは難しいかもしれませんが、いらないものはいらないとはっきり断ることが大切です。
また、商品の販売経験がない者が行う契約ですので、トラブルが多く、人間関係を壊したり、ご自身が加害者となるケースもあるため、細心の注意が必要です。
相談4
外出先の駐車場で車のバッテリーが上がってしまったため、インターネットでロードサービス業者を検索し、「バッテリー修理 1,980円~」等の表示を見て業者を呼んだ。現場に来た業者は、「バッテリーの電圧を調べるのに9,000円。」と説明したので、高いと思ってキャンセルしようとしたが、業者から、「バッテリーの修理には8万円。今からキャンセルすると、バッテリー点検料9,000円とキャンセル料6万円の合計6万9,000円かかる。」と高額な請求をされ、トラブルとなりました。
この相談の事例は、訪問販売に該当し、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフが認められます。
自動車の故障に限らず、トイレ詰まり、害虫駆除、鍵の開錠等の暮らしのレスキューサービスを利用する際は、訪問を依頼する前に、費用や作業内容等の契約条件をよく確認しましょう。