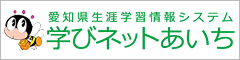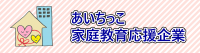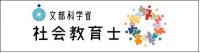本文
「親の育ち」家庭教育支援者養成講座を開催しました
乳幼児から小中学生をもつ親の子育てについて地域で気軽に相談に応じたり、子育てグループや子育てサークルの活動を支援したりする「子育てネットワーカー」を始めとした家庭教育支援者を養成・育成しています。
その開催結果を報告します。
<令和5年度「親の育ち」家庭教育支援者養成講座>
令和5年度は、90名の方の受講があり、そのうち69名の方が修了認定を得られました。
また、令和3年度から単位制としていますので、複数年にわたり単位と修了証の取得が可能となりました。
☆ 令和5年度「親の育ち」家庭教育支援者養成講座の詳細についてはこちら >>
| 開催日 | 内 容 |
|---|---|
| 令和5年9月20日 (水曜日) |
単位E:家庭教育研修会の講座運営の方法、「親の学び」学習プログラムの活用について 講師:豊川市子育てネットワーカー 志村 貴子 氏 |
|
単位F:PEP TALK! ~やる気を引き出す言葉の力~ |
|
| 令和5年9月26日 (火曜日) |
単位B:子供の特性と保護者支援:児童期・思春期編 |
|
(1)(行政説明)県の家庭教育支援施策の動向 (2)(事例発表)地域で子供の成長を支えよう (3)(事例発表)子育てネットワーカーの活動の実際 |
|
| 令和5年10月5日 (木曜日) |
単位A:子供の特性と保護者支援:乳・幼児期編 |
| 単位D:家庭教育支援の実際と団体の自立的運営 講師:NPO法人Smiley Dream 顧問 櫻井 雅美 氏 |
| 講座概要 |
|---|
|
☆ 単位E:家庭教育研修会の講座運営の方法、「親の学び」学習プログラムの活用について 
子育てネットワーカーとして長く活躍されている講師から、自身の経験や実践を基に、子育てネットワーカーの活動内容をはじめ、その意義やめざす姿についてお話しいただきました。また、「あいちっこ『親の学び』学習プログラム」を活用したグループワークを実際に行い、ワークショップの進め方やアイスブレーキングの方法等を体験しました。講義やグループワークを通して、講座運営のノウハウはもとより、子供目線で言葉を選ぶことの大切さや講師としてどのように参加者の意見をまとめるのかなど、子育てネットワーカーのやりがいや魅力を実感をもって学ぶことができました。 |
|
☆ 単位F:PEP TALK! ~やる気を引き出す言葉の力~
|

児童期や思春期の特性や発達課題を踏まえた保護者支援のあり方についてお話をいただきました。不登校の児童生徒が増えてきている現状をふまえて、傷つきやすい子供の良いところを見つけるには、「違う側面に目を向け、ポジティブな言葉に言い換え励ます」ことや、「大人が言葉を補う」ことが、子供の自信と安心のもとになること等を教えていただきました。また、グループワークでは、「子育て(支援)の中で直面した出来事」への対応について、意見や助言を交換することをとおして、保護者との関わり方や支援のあり方についての考えを深めることができました。 |

愛知県の行政説明では、アウトリーチ型支援の役割や活動内容を紹介するとともに、家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」について説明しました。また、事例発表では、半田市が2019年から全小中学校で導入しているコミュニティ・スクールの取組において、家庭教育支援にかかる取組を地域ぐるみで行っている事例について学びました。幸田町の子育てネットワーカーの1年間の取組について、動画を視聴したり、企画プログラムの構成の工夫について、考えを深めたりすることができました。 |
|
|

家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」事業を展開されている講師より、支援団体の立ち上げの経緯や活動事例、運営の工夫等について、質疑応答を交えながら、支援のあり方や活動の進め方等について、自身の体験や実践を基に具体的に説明していただきました。「自発的なコミュニケーションを促す工夫」や、「行政のどの部分を市民団体として担っているのか」などの説明をとおして、受講者は支援の意義や魅力、「ホームスタート」の有用性を実感をもって学ぶことができました。 |
| 参加者の声 |
|---|
|
これまでの開催講座について紹介します
令和2年度までは「親の育ち」子育てネットワーカー養成講座と「親の育ち」家庭教育支援者スキルアップ講座を隔年で開催していました。
令和3年度からこの二つの講座を一本化しました。
<「親の育ち」家庭教育支援者養成講座>(令和3年度から名称変更)
R04「親の育ち」家庭教育支援者養成講座の様子 [PDFファイル/520KB]
R03「親の育ち」家庭教育支援者養成講座の様子 [PDFファイル/366KB]
<「親の育ち」子育てネットワーカー養成講座>
「子育ての中の家族の相談相手や子育ての応援をしたい。」と考えている人に、家庭教育支援や子育て支援の基礎を学ぶ講座を開催します。
<「親の育ち」家庭教育支援者スキルアップ講座>
「あいちっこ『親の学び』学習プログラム」を活用した家庭教育研修会の講師を務めることができるよう、知識・技能の向上を図る講座を開催しました。

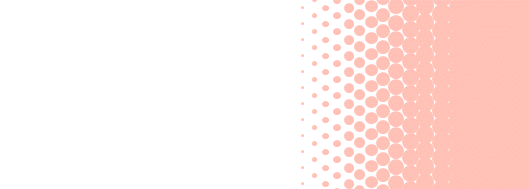
 端的で肯定的な言葉「PEP TALK」(ペップトーク)を使い、できるだけ短く、分かりやすく人に思いを伝えるコツについてお話しくださいました。否定的な意味をもつ言葉を肯定的な意味に捉え直す研修や、他者から自分を認めてもらうグループワークをとおして、やる気を引き出すためには、子どもの好きな部分や長所を認めた後に成長できる点について声をかけるという順序を意識したコミュニケーションや、大人が自分を大切にすることが子供を本気で応援することにつながることなど、支援者としてのあるべき姿について学ぶことができました。
端的で肯定的な言葉「PEP TALK」(ペップトーク)を使い、できるだけ短く、分かりやすく人に思いを伝えるコツについてお話しくださいました。否定的な意味をもつ言葉を肯定的な意味に捉え直す研修や、他者から自分を認めてもらうグループワークをとおして、やる気を引き出すためには、子どもの好きな部分や長所を認めた後に成長できる点について声をかけるという順序を意識したコミュニケーションや、大人が自分を大切にすることが子供を本気で応援することにつながることなど、支援者としてのあるべき姿について学ぶことができました。 講義では、0か月から6歳までの子供の特性について、エリクソンの発達理論をもとに、具体的な姿を挙げながら、子育て支援のポイントについてお話しくださいました。「自分自身の基本的な枠組みは乳幼児期に形成される」「日々の子育ての関わりの中で自己肯定感が育つ」「親の語りかけ方で子供は変わる」とのお話から、これまでの自身の保護者に対する見方を振り返るとともに、子育てネットワーカーとしてのあるべき姿を考える機会となりました。
講義では、0か月から6歳までの子供の特性について、エリクソンの発達理論をもとに、具体的な姿を挙げながら、子育て支援のポイントについてお話しくださいました。「自分自身の基本的な枠組みは乳幼児期に形成される」「日々の子育ての関わりの中で自己肯定感が育つ」「親の語りかけ方で子供は変わる」とのお話から、これまでの自身の保護者に対する見方を振り返るとともに、子育てネットワーカーとしてのあるべき姿を考える機会となりました。