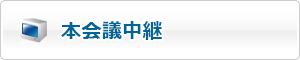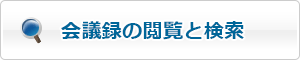本文
デジタル化・地方創生調査特別委員会審査状況(令和6年11月21日)
デジタル化・地方創生調査特別委員会
委員会
日時 令和6年11月21日(木曜日) 午前10時~
会場 第8委員会室
出席者
神野博史、朝倉浩一 正副委員長
直江弘文、高桑敏直、石塚吾歩路、山下智也、新海正春、成田 修、
かじ山義章、谷口知美、細井真司、加藤貴志、井上しんや、末永けい 各委員
金子 隆一 参考人(明治大学 政治経済学部経済学科 特任教授)
政策企画局長、企画調整部長、関係各課長等

委員会審査風景
議題
人口減少社会の実相と処方を考える
会議の概要
- 開会
- 委員長あいさつ
- 議題について参考人からの意見聴取
- 質疑
- ペーパーレスによる委員会運営の試行について
- 閉会
参考人の意見陳述
【参考人】
本日は、このような場にお招きいただきまして、本当に光栄に存じます。
各界の指導的な立場におられる皆様に人口の問題をお話しできるということで、ちょっと舞い上がりまして、あまりにも多くの題材を持ってきてしまいました。時間の中で収まるかどうか分かりませんが、なるべく重要な部分をかいつまんでお話をしていきたいと思います。
人口問題に関しては毎日のように報道されているのですけれども、全体像というものを見る機会が非常に少ないです。それで、そういったことが見通しよく見られればということで、少し全体像みたいなことをお話ししたいと思います。お話のアウトラインとしましては、人口動向、それからその動向のもたらす課題、そしてそれに対する手法という、三つの部分でお話をできればと思います。
歴史的に見ますと、資料3ページの世界人口のグラフでございますけれども、御覧のように、産業革命以降の近代化の過程におきまして現代の人口というものがほとんど形成されたという形でございます。最近の世界的な専門家の見方によりますと、今世紀中に人口減少が始まるのではないかというように見られております。一方、日本の人口を歴史的に見ますと、幕末から明治期にスタートした近代化とともに人口が増えていく。これは、世界人口と同じような推移をしております。
問題はこの先なのですけれども、スライドと資料4ページを御覧いただきますと、やはり世界人口のようにこういう推移をするのかなと思うわけですけれども、実際に政府の推計によりますと、御覧のような形になっております。このグラフの意味するところは、日本の社会というものが人口とともに大きな転換点を迎えている。世界もこれまでの成長・拡大というフェーズから、その終焉と若干の減少という大きな転換を迎えるわけですけれども、日本はいち早くもう既に人口のピークを越えているわけであります。
問題は、こんなに人口が急激に減って、社会が持続可能なのかどうかという問題になろうかと思います。明治時期以降の21世紀を通しての現在を中心にした人口を拡大しますと、御覧のような富士山の断面図のようなきれいな左右対称のグラフになります。人口が増えてきたフェーズとこれから減っていくフェーズ、そのペースがほぼ同じなので対称形になるのですけれども、その中身というものが、御覧のように上り坂と下り坂では全く違っている。特にこの紫色で示した高齢者、上り坂ではこんなに少なかったのです。それが、下り坂では御覧のような形になっている。人口は大きく減っていくのに、高齢人口はそんなに減っていくように見えない状況にあるわけです。
このグラフが意味するところは、人口問題というのはこの上り坂でつくってきた日本の社会の仕組み、特に社会保障制度など、果たして下り坂で機能していくのかと、その一言に尽きると思います。結論を申し上げれば、そのままで仕組みが機能することは恐らくないだろう、大きな再構築が必要になってくるということを訴えている、このグラフはそのように見えるわけでございます。
その年齢構成、人口高齢化というものをより視覚的に見るためには、資料5ページ人口ピラミッドの変遷を御覧いただくのが一番よいかと思います。1950年の時代に生まれていた人は、今、74歳以上で、2,000万人ぐらいおり日本の人口の中で、まだ大きな割合を占めています。したがって、そんなに昔の時代ではないのですけれども、かなり前近代的な形をしています。
21世紀に入ると人口ピラミッドが動きます、2020年でこのような形になる。今、こんな形をしているというところです。大きく変わりましたのは、高齢人口のところが大きく横に広がっています。数字でいいますと、この時点で26.6パーセント、現在はもう29パーセント代ですから、ほぼ3割になろうかというところです。この時点でもう、圧倒的に世界一の高齢化率ということになっています。しかし、まだこの時点では、青い生産年齢人口が比較的豊富にいるように見えます。団塊ジュニアがまだ頑張っている感じです。
問題は、この先なのですが、御覧のように、これからはどんどん人口が減っていくために人口ピラミッドの面積が減っていき、重心がどんどん上に上がっていく。これが2070年の状況でございます。一番多い人口の多い世代に高齢層が入ってくる。高齢者の割合が4割近い。しかし、今世紀後半に入りますと、もう人口の形自体、すなわち年齢構成自体はもうそれほど変わりません。ただし、人口減少はさらに続きまして、2100年ではこの形のまま縮んでいくのではと懸念されているわけであります。
人口の変動は世界的に見てどうであろうかということですが、資料7ページを御覧ください。1950年から21世紀を通しての世界人口の内訳と規模を円グラフで表したものですが、一番左の1950年ですと、日本の人口は世界第5位になっており、日本はかつて人口大国でありました。ところが、現在は12位にまで下がっている。
1950年から時が進むにつれ、次第に世界人口が増えてくるとともに、内訳が少しずつ変わってきています。初めはアジアの人口が増えましたが、今世紀半ばから後半にかけましては御覧のようにアフリカの諸国の人口の増え方が著しいです。したがって、2100年の世界の内訳というのは、どうも我々の知っている世界とはちょっと違うものになっていきます。今世紀半ばから後半にかけては、アフリカの時代というものが世界の中でやってくるといえる。人口だけでそういうことが決まるわけではありませんが、ほかの指標を見ても、アフリカの躍進というのは目覚ましいものがあるであろうということが見込まれているわけです。
この中で、日本はどこ行っちゃったかという感じですけれども、2100年では0.5パーセントということで、順位がもう20位とかよく分からないぐらいになっているはずです。これが、少し先まで見通した世界と、その中の日本ということでございます。地政学的な事情は大きく変わると思います。
資料8ページ、世界人口を改めてこういったグラフで表しますと、真ん中にある縦線が現在と思っていただいていいのですが、今後もどんどん増えていく。しかしながら、一番右端が2100年ですが、今世紀中にピークに達するであろうという推計が国連から出されています。ここ5年ばかりの間に公表された推計ではそういうことになっている。それまでは、世界人口は増え続けるという見通しだったのです。ですから、本当にここしばらくの人口の状況によって大分見方が変わってきている。
これは、世界全体で今世紀中に減り始めるだろうということですが、ちょっとアフリカは先ほど見たように特異な部分がありますので、アフリカ以外の人口を見ますと、なんと2053年にはもうピークに達してしまう。ですから、世界人口の減少というのも、もうそんなに遠くないぞというような状況にだんだん至っております。それまでは、日本とか韓国とか中国とか、東アジアの国々とか、イタリア、ドイツとかは、特別、出生率が低くて特別な国だと見られていたわけですけれども、少し見方が変わってきて、これは、人類全体の傾向ではないかというふうに見られてきているということでございます。
個別の国を見ますと、資料9ページが中国の人口グラフなのですけれども、先ほどの日本の富士山の断面図と申し上げた図と同じ種類の図と非常によく似ております。既にピークを過ぎ、人口減少が始まったところであります。この中に先ほどの日本の富士山の図を同じスケールで入れてみます。御覧いただけましたでしょうか。下のほうにあるのが日本です。人口には、同じようなことが中国でも起こりますが、規模がまるで違います。こういった大規模な変化がお隣の国で起きるということは、日本は日本の人口問題だけ考えていればいいわけではないちょっと懸念を呼ぶわけです。実際、中国の高齢者人口、最大のところでいうと総4.3億人ですから、日本の人口の3倍から4倍近い数の高齢者がいる状況が隣の国で起きていくということです。
資料10ページがインドの人口グラフです。これまた人口大国で少しピークが遅れますが、やはり同じような推移をすると見込まれています。この図の中に日本を入れてみますと、やっぱり、全然規模が違う。ですから、お隣とそのお隣の国でこのような大規模なことが起きていく。ほかの国のことだから知らないよというわけには恐らくいかない。このグローバル化の中で大きな影響を日本も日本の高齢化、人口減少とともに受けることも考慮していかなくてはいけないということでございます。
それから、高齢化についても世界的な情勢を見ますと資料12ページ、これは世界の全ての国の高齢化率、65歳以上人口割合の1950年から2100年の推移でございますけれども、この真ん中の線が現在ということで、これで見ますと、明らかに現在以降、世界の全ての国で例外なく高齢化が起こる。ですから、21世紀の現在から後はもう、世界中で高齢化の世紀になるといっても過言ではありません。
ただし、その高齢化のレベルやペース、これは随分国によって違います。日本はどうなのかというと、御覧いただけるように赤い線ですけれども、現在においてはもう並ぶもののない高齢化国ということになっています。世界一の高齢化国だということはよく知られているのですけど、ここまで第2位を引き離した圧倒的な高齢化国であるということはなかなか理解されていないようです。ただ、今後は、韓国、中国が非常に出生率が低いということがありまして、高齢化率でも我が国に追いつき、追い越していく状況にございます。
ですから、くしくも東アジアのこの3か国が、向こう100年ぐらいにわたって、世界の高齢化という状況を先取りした社会として先頭を歩んでいくということになります。特に日本がそうですけど、課題先進国ということになります。ですから、パイオニアとしてほかの国の経験したことのないことに対処していかなくてはいけないわけですが、もしそこでうまく対処ができれば、これはもうその後の世界におけるモデルになる、日本モデルとして一種のビジネスモデルのように、世界中に売れるモデルになるということです。だから、大きなピンチであるもののチャンスであることは間違いない状況にございます。
あとは、高齢化のペースが著しくほかの国と違っておりまして、資料13ページに示しましたグラフでは、高齢化率が7パーセントから3倍の21パーセントになるのに何年かかったかというものです。欧米の先輩国たちを見ると、フランス156年、スウェーデンが140年、アメリカ90年、ドイツ84年となっております。ところが、日本37年、中国33年、韓国26年と、著しく短い期間でこの高齢化を経験していくわけでありますから、直ちに対処し、どんどん社会を変えていかなくては間に合わない。そういう懸念を抱かせるデータでございます。
資料15ページ、パラドックスと書きましたけれども、幾つかふだんあまり語られない部分を見てみたいと思います。まずは資料15ページ下の部分、出生数と死亡数のほうでございますが、これが年間出生数の年次推移でございます。戦時中、ちょっと空いてるところがありますが、戦後は第一次ベビーブームがあり、第二次ベビーブームがありというところがよく御覧いただけるかと思います。
第二次ベビーブームというのは、御覧のとおり、第一次ベビーブームの世代が親になり、したがって親の数が多いので子供が多いという形で、第二次ベビーブームがあったわけでございます。そこから現在まで出生数が並べてございますけれども、ここでちょっと違和感を持つのは、第三次ベビーブームはどこに行ってしまったのかということです。親が多ければ子供が多いということであれば、第二次ベビーブームの人たちが親になる時期、1990年後半から2000年代前半ぐらいにかけて第三次ベビーブームがあってしかるべきです。ところが、それがなくなっている。それはなぜかというと、その時期に人々の行動パターンが大きく変わりました。結婚離れが進み、晩婚化が進み、そして結婚しない割合が増え、子供を持たない割合が増えました。
それがこの黒い線のグラフです。これは合計特殊出生率という指標ですけども、これは各年次の行動パターンの強さを表す、出生行動の強さを表す指標ですが、それがちょうど第二次ベビーブームが子供を産む時期にがくっと下がっております。つまり、親となる数は多かったけれども、結婚や出産から少し離れたために、ここに第三次ベビーブームは起こらなかったということになります。それが少子化という形で捉えられたわけです。したがって、これまでの少子化というのは、若い世代が、結婚しない、出生しないという行動パターンの変化によって現れました。
これからはどうなんだという将来推計も描いてますけれども、行動パターンのほうはもう変わらないという見込みになっています。行動パターンのほうは変わらない、安定化するという見込みになっているにもかかわらず、出生数のほうは著しく減っている。これはどういうことかというと、行動パターンはもうそんなに変わらないという見込みなのですけれども、今後は構造要因が関わってくる。親の数がもう既に現実問題として大きく減ってきています。現在までに生まれた子供の数を見れば、これから30年先までの親の数というのが大体分かるわけです。現在生まれた子供たちは、30年先の赤ちゃんたちの親になる。行動が変わらないということは、出生数は親の数で決まるということですから、これからも少子化は御覧のように厳しく続いていきますけれども、これまでと違って、親が減っていくことによって少子化が続いていくことです。
ですから、これまでは行動パターンを変えるために、何か行動を変えさせるような政策というものを考えられたわけですけれども、これからはそれだけでは駄目であります。構造的に減っていってしまうため、かなり厳しい段階に入ったということが言えるのではないでしょうか。
一方の年間死亡数のほうは、現在急速に数が増えています。これが多死社会の到来という形で言われているわけですけれども、著しい増加を毎年しているわけです。日本人は、年々健康になり、平均寿命もまだ延びているという状況の中で死亡数は増えていくというのは、非常にパラドキシカルなことです。
もうちょっと踏み込んで説明をしますと、グラフを死亡年齢によって色分けしております。戦前、御覧いただきますと、戦前も120万人、130万人という年間死亡数があったわけですが、誰が死んでいたのかというと、黄色の部分の子供です、それからブルーの部分の働き盛りです。ですから、死亡数の7割か8割は若い人たちの死亡だったわけです。高齢になって亡くなるって方は、戦前は2割とか3割ぐらいしかいなかったのです。それが戦後になって大きく事情が変わりました。子供の死亡が一気になくなりました。働き盛りの人の死亡数も大きく減った。その分だけ全体の死亡数が減ったわけですが、人間は必ず死にますので、最終的には必ず同じ数だけの死亡が起こるわけですが、この減った部分はどこに行ってしまったかというと、子供の死亡が減れば大人になれる人の数が増えた。ですから、この戦後すぐというのは、若い労働力がどんどん増えたわけです、子供が死ななくなったことによって。その人たちが長生きして、そして現在、死亡するフェーズに入っている。ですから、戦後すぐのこの減った分、積み残した部分が一緒になって死亡が増えているということになります。ですから、まだまだ死亡は増えていく。
この死亡が増えていくということの意味ですけれども、ビジネス的に見ると、やはり葬儀関係の業界が潤うじゃないかっていうような短絡的な見方もできます。それから行政の立場からいいますと、火葬場を準備することも課題ですけれども、もう一歩深く考えると、死亡に近い人口が増えるっていうことがとても問題なわけです。専門用語でいうと、終末期の人口がこれからどんどん増えていく。つまり終末期医療と終末期介護、そういったものの需要が大きく増えていくということをこの図は含意しているわけであります。死亡数が増えて出生数は減り続けるということですから、人口は急速に減っていきます。この状態を何とかしない限りは、人口の増減というのは変わらないということになるわけです。
もう一つ、人口を見る上で一つパラドキシカルな、なかなか理解されない部分なのですけれども、人口減少の原因は何か。これはもう、ひとえに少子化でございます。少子化が直接の原因ですから、原因を取り除けば結果はなくなる、つまり人口減少は起こらないだろうと考えるのが普通でありますけれども、果たしてそうかということでシミュレーションをしたものが資料18ページであります。青いラインは政府の将来推計そのもので、少子化が現在のように続いていった場合です。赤いほうは2015年以降、少子化が完全に解消したら人口の推移はどうなるかというものです。赤いラインをみると人口は減っています。少子化を解消したら、人口減少は解消するはずでしょう。何かおかしいのではないかということですが、この図で見ても、2070年代ぐらいまでは減り続けていることが明らかです。
なぜか。それは、人口というものを決めるのは、先ほども出てきたのですけども、行動だけではなくて構造がとても重要な働きをするからです。構造とは何か。人口ピラミッドの形でございます。人口のピラミッドの形を政策でもって急激に変えることはできません。人口ピラミッドの形を変える政策をとって成功したとしても、実際に人口ピラミッドの形が目に見えて変わるのは30年後、50年後になります。
ですから、人口ピラミッドのほうは変えられないのですが、この人口ピラミッドの形が毎年の人口増減に大きな影響を与える。つまり親の数が減っていけば、一人一人が多少子供を多く生んでも、そもそもの親の数が減っているわけですから子供の数が減っていく。だから、行動が変わっても子供は減っていく。それから、死亡数のほうを考えても、寿命は延びている。一人一人は長生きになっているのだけれども、高齢者がどんどん増えていくということになれば、結果として死亡数は増えていくわけです。
ですから、グラフの左下に書いてありますけども、人口ピラミッドの形が毎年の人口変化に大きな影響を及ぼしますので、その影響が出るために少子化が完全に解消した、異次元の少子化対策が完全に成功したとしても、人口は減り続けていく。ですからもう、人口が減っていくということは、ほぼ避けることができないということであります。
ただし、もし少子化が完全に今解消したのであれば、恐らく今世紀の末には人口の推移が御覧のように安定化する。人口ピラミッドの形もそれまでには変わっていく。しかし、このまま少子化が解消しなければ、政府の推計のとおりどんどん人口ゼロに向かっていく。これがとどまる根拠というのは、今のところはないということになります。
このシミュレーション、示す意味合いというのはいろいろあるのですが、一言でいえば、人口政策が人口にあたえる影響は、来年からすぐに問題を解決できるっていうものは非常に少なくて、仮に大成功しても成果が出るのは30年後とか50年後とかになってしまう。だから、やや政治と親和性がよくない。言ってみれば100年の計でやっていかないと影響を与えられないという、そういう非常に難しい性質を持っているということを示しているわけです。
ですから、少子化、この人口問題に対処していくためには、緩和策と適応策の大きく二つの異なるタイプの政策を考えていかなくてはいけないということになります。今、人口の減少あるいは高齢化が進んでいる一番の原因は少子化ですから、これを解消しない限りは永久にこの問題は解決しない。だから、少子化に対処をしていかなくてはいけないということが、本質的にはあるわけです。
しかし、資料のとおり、仮にそれが大成功しても、成果が出るのは30年、50年という長いスパンで見なくてはいけない。しかし、目の前で人手不足をはじめとしたいろいろな人口問題の課題が現実に生じているわけで、それには別途、人口変化の結果に対してどんどん適応策を打っていかなくてはならず、この両方を両立していかなくてはいけないということです。ボートが水漏れをして沈みそうになっているという状況のときには、水漏れをしている穴を探してそこを塞ぐということが必要ですが、それよりも先に、入ってきた水をどんどんくみ出すということも同時にやらないと沈んでしまいます。現在はそういう状況にあるということを申し上げたいと思います。
次に、地域別にどんなことがあるのかと、課題があるのかというのを見たいと思うのですが、資料21ページのグラフは、65歳以上の人口を、実数を都道府県別に多い順に並べたものです。当然、人口の多い東京、神奈川、大阪、愛知というのが上位になります。これ、二つ実はラインが引いてありまして、黄色が2010年、赤が2040年の高齢人口なのですが、黄色と赤の差を御覧いただくと、この間の高齢人口の増加の実数が分かるわけです。大都市でとんでもない数になっている。愛知県は上から4番目です。愛知県も、名古屋、中京都市圏にありますので、大都市の一部として大量の高齢者が増えていくということが見込まれている。
一方で、下位のほうです。これまで高齢化がとても問題になっていたような、いわゆる地方と呼ばれる県においては、御覧いただけるように、高齢人口はほとんど増えない。むしろ減っているところもあるということです。秋田県、島根県、高知県なんかは、2010年から2040年の間にもう高齢者が減っているんです。じゃあ高齢化は終わりかというと、そうではなくて、高齢化率は増えていく。
高齢人口が増えないのに、何で高齢化率が増えるのか。それは、若い人が高齢者よりもどんどん減っていくからです。つまり、下位のほうの地域は、いわゆる人口消滅と、地方消滅と呼ばれるような状態に陥りつつあるということです。ですから、大都市圏と地方圏では問題が大分ずれてきているということが言えます。
資料22ページは、認知症患者数の推計を同じように都道府県別に示したものですが、先ほどの高齢者の数よりもずっと多い割合の認知症の増え方になっています。高齢者がもう増えない地域でも認知症患者が増えている。すごいパラドックスです。これは、高齢者人口の中でもより高齢の人口の増え方が著しいという、高齢化の特徴があるからです。つまり、65歳以上人口は同じでも、85歳以上とか、より年齢の高い人口はこれから増えていくわけで、高齢者の中で高齢化が進んでいくわけです。ですから、高齢人口は変わらなくても、認知症の患者数はどんどん増えていく。ほかの要介護度などもそうですし、年齢とともに悪化が生じるものは、こういった同じ状況になるということでございます。
都市部では、介護難民問題というのがこれから大きな問題になる。それから地方圏では、地方消滅のリスクが大きくなっていく。これは、例えば愛知県で考えた場合、愛知県は、まるで日本全体の縮図のような県だなと私は思っているんですけれども、大都市圏と地方圏の課題の両方を含んでいる県だと思っております。
人口戦略会議というのがこのところ立ち上がりまして、政府に対して提言をしているところでございます。私もそのメンバーの一人ではありますけれども、その人口戦略会議が今年の4月に発表したのが、資料23ページの下の地方自治体の持続可能性マップとリストというものになります。消滅可能性自治体は人口の減り方が著しく、今後、20歳から39歳の女性人口が30年で半分になってしまうような自治体は危険信号ですよということで、消滅可能性自治体と名前をつけてリストアップしています。これはいろいろと物議をかもしたところでございますけれども。御覧のように、日本中にそれは散らばっているということになります。
もっと一般的な何か法則性みたいなものはないのかということで、資料26ページの図なのですけれども、これは2010年と2050年の二つの時期について、都道府県について、横軸が高齢化率、そして縦軸が人口増加率です。つまり、人口高齢化と人口の減り方、増え方の関係を見たものです。2010年のほうを見ますと、高齢化している地域ほど人口の減少のスピードが速いというのが御覧いただけます。2050年に至っても、その関係は変わらない。変わらないけれども、47都道府県がまとまって右下のほうに動いているのは御覧いただけると思います。つまり、全てが高齢化し、全てが人口減少に向かうということです。
途中に横線、赤い線がありますが、これが水面といいますか、これより上だと人口増加で、これより下だと人口減少です。もう2050年では東京でも水面下となる。このように大きく全体は変わっていく。しかし、高齢化しているほど人口減少が激しいという傾向の相関です。因果関係と言っては間違いですけれども、相関は保たれているということでございます。
これを、先ほど日本の縮図と申し上げましたけど、資料27ページの愛知県の中で見ますと、やはり同じような傾向があり、高齢化が進んでいる市区町村ほど人口の減少が著しいということでございます。実はまだ一部しかこれ描いてなくて、愛知県全体を描きますと、追加資料を後日配付したいと思いますが、スクリーンにあるものが県全体の市町村の散布図です。そうしますと、右下のほうに著しく離れたところがありますが、著しく高齢化して著しく人口減少が速い地域というのがあるわけです。御覧のように、大都市圏で人口がまだ増えているところもあれば、著しく高齢化し減少が進んでいるという、多様性が非常に大きいのが愛知県の特徴ではないかなというように思われるわけであります。
なお、これは愛知県の人口ピラミッドの変化をスクリーンと資料28ページのほうではお示ししているわけですけれども、日本全体の変化とよく似ていますよね。ほかの地域と比べると愛知県の変化は比較的穏やかである。資料29ページ、岡山県の人口ピラミッドは中間的な変化なんですが、2045年ぐらいになると大分働き盛りが減っているというのが分かる。さらに高齢化と人口減少が一番厳しい秋田県と同じぐらい厳しい山形県を見ますと、御覧のようにやっぱり明らかに見て違いがあります。しかしながら、これは時間的なずれがあるだけで、いずれ日本全体がこの形になっていくというような今のところ見通しということになっているわけです。
その影響について、よく言われるのは、人口ボーナス、人口オーナスです。人口ボーナス、オーナスを表す指標に、従属人口指数というのがありまして、これは何かというと、社会には社会を支える人々と社会に支えられる人々がいます。例えば、赤ちゃんは社会を支えてないですよね、支えられるしかない。学齢期にある子供は支えられないといけない。それから、引退した後のお年寄りも支えられなくてはならない。だから、支えられる人口を分子にもっていって、それを支えている働き盛りの生産年齢人口を分母に取る。
そうしますと、働き盛りの人が、自分以外に何人を支えなきゃいけないかという指標になります。戦前を見ますと、70パーセントになっています。これは、働き盛りの人が、0.7人自分以外に支えなきゃならない社会ですよということです。これが戦後急激に下がっています。これが人口ボーナスと呼ばれる現象で、社会の支えなきゃいけない負担が大きく下がった、これは経済にとっては非常に有利な状況です。働き盛りの人の負担が減ったということですから。何で減ったのかというのは、先ほどもちょっとお話ししたのですけど、戦後、子供の死亡が一気に下がった。それによって、それまで死んでいた子供たちがみんな大人になれるようになったという話をしました。したがって、若い働き手が一気に増えたんです。これが人口ボーナスです。
実は、これは日本だけではなくて、近代化すると大体同じような現象が起きる。人口ボーナスが必ず一度来ます。しかし、一度しか来ません。その後は、増大した若い働き手も四、五十年するともう高齢者になるわけですから、その後の補充がなければ、若い世代、働き手をどんどん補充しなければ、高齢者が増えていくわけです。どこの国も、日本をはじめとして新しい世代を補充しなかった、つまり少子化です。ですから、御覧のように従属人口指数はうなぎのぼりになっていって、100パーセント近くまで行く。働き盛りの人が自分以外に丸々もう1人支えなきゃいけない世の中が来るということを、この指標は示しているわけであります。
これは、先ほど申し上げましたように、世界的にもどの国にも起こることなんですが、人口ボーナスが起こる時期が、例えば近隣の国で描きますと、資料33ページのようにへこんでいるところがずれています。現在、日本はとっくにもうへこんでいる部分が終わって上り坂になっているわけですけども、今、韓国、中国がへこんでいる部分が終わりかけているところです。これから従属人口指数がどんどん上がっていく。その頃になりますと、マレーシアやインドが一番へこんでいるところになり、一番経済にとって有利になる。それらの国も従属人口指数がまた上がっていき、人口オーナスに向かっていくわけです。その頃にはパキスタンが今度は人口ボーナスになる。このように、世界中で人口ボーナス、オーナスが波のようにうねります。
資料34ページ、1950年から2100年の世界中の全ての国の従属人口指数を三次元グラフにして地域別に並べてあるんですけれども、一番手前に赤い板として日本が示してあるからお分かりになると思うのですが。この一番へこんだところは白く見え、谷になっています。これが斜めに走っているってことは、人口ボーナスが世界中で次々国を移っていくということです。今世紀で最後に大きな谷になっているのが、アフリカということになります。今世紀の後半になりますと、アフリカで大きな人口ボーナス、しかも長くて深い人口ボーナスが起きてくる。
こういう世界情勢の中で、日本などはもうとっくに人口ボーナス終わってオーナスになっていることですから、とてもじゃないけども、一国としてほかの国々と経済競争していくことはもう無理です。じゃあどうするんだと、これはもう連携するしかありません。例えば、若い労働力がたくさんいるけれども、まだ資本の蓄積が十分でない途上国と日本のように、もう若い労働力がないが資本の蓄積はあるぞというような、それぞれのいいところを連携するようなことをしない限りは、なかなか世界経済の中で生き残っていくのは難しいという状況をこれは表しております。
それからよく言われるのが、シルバー民主主義です。資料36ページの表は、有権者の中での高齢者の割合を赤い四角の中で表しました。1960年から比べると、現在はもう3倍以上の割合になっています。ですから、もう既に有権者人口の中での高齢化ということはもうどんどん進んでいく。子育て世代、35歳未満を見ると、全くそれと逆のことが起きていて、かつては4割以上いたのが現在はその半分以下の19パーセントです。将来的に見ると、高齢化の割合が半分に近いところまで行く。これが有権者の人口構造の変化なんですが、実際の政治的な意思表示というのは、投票ということをしないと有効にならないので、投票率というのもあります。
資料37ページ、左側のグラフは投票率ですけれども、年齢別に大きく違うわけです。ですから、よく見ると、60代、70代の投票率が一番高くて、20代の投票率が低い。ということは、人口が少ない上に、投票率も低いということで、例えば、一番多い70代前半と20代前半を比べますと、500万人違うわけです。700万票に対して200万票ぐらいですから、もう圧倒的な差がある。ですから、仮に対立するような案件があったとすれば、なかなか若い世代の意向が十分に達成できないのではないかと思います。
昨今ありました東京都知事選においては、年齢層によって支持する候補者が大きく違ったということがあります。これに対して、この人口構造がどういう影響を与えたかということをいろいろ考えさせるものがあるわけです。また、今般の衆議院総選挙がありましたが、ここでは国民民主党というキャスティングボートに対して支持をするという形で、少数であっても発言力を増すという、若い世代が発言力を保つ一つの方式というのが今回ちょっと見られた点で、すごく興味深かった。
また、先週、兵庫県の知事選もありましたけれども、ここでは若い世代が今度は別の形でSNSによって情報を拡散する媒体になった形でも発言力を増す方式があった。またこれもいろいろ考えさせるものがあるのですけれども。いずれにせよ、国民の意思決定をどのように政治に生かしていくかということで、有権者の年齢構造の変化っていうことを少し考えていかなくてはいけないのかなというところであります。
これ、一般化して考えますと、実はプレストンという学者が、人口高齢化すると社会の資源配分がどうしても高齢世代に偏りがちになりますよということを早々と、1970年代にそういった理論を言っていたんですけれども、確かに有権者人口の高齢化ということが起きている。これが実際にどういう影響になっているかというのをちょっと検証しないといけないんですが、しかし原理的にはどうしても世代間の不公平性の問題を生じるような方向に働くであろうと思います。
さらに問題なのは、経済の分野で市場原理というのがあります。市場原理も、政治と同じで多数決原理ですよね。ですから、世代で全く異なる利害のあるような懸案がありますと、そこで対立をする。ですから今の社会システムですと、政治の面でも、それから市場経済の面でも、若い世代というのはどうしても不利な状況に置かれるという傾向が見られるわけです。
それ自体も重要なんですけれども、それがどういう課題を生むかというと、一番懸念されるのは、若い世代というのは家族形成の世代ですから、その世代が不利を被ってしまうと少子化がさらに進んでしまう可能性があるわけです。少子化というのは高齢化を進める最大の促進要件ですから、さらに高齢化が進む。高齢化が進むと、若い世代が割を食う。そうすると、少子化が進む。これはもう完全な悪循環です。少子高齢化トラップと名づけましたけれども、もしかすると現在の社会はこういう状況に陥っている可能性があるのではないかというあたりを、少しみんなで考えたいなと思うところであります。これを抜け出すのは、恐らく相当思い切ったことをしないと難しいのではないかと思います。
それから、ちょっと話が変わりますけど、人口減少というのは、グラフで見てこれは大変だと思うわけですが、それ、グラフ上のことではないですよ、あなた自身のことですよという話です。人口減少というのは、私たち一人一人にどういう形で現れるかというのを一つの例として資料41ページに表しています。右上のグラフは、1940年生まれ、つまり現在でいいますと、84歳の世代が生涯に何人子供を産んだか、何人孫を持ったかの分布を表しています。その子供の世代、1970年生まれ、現在54歳、これも生涯の子ども数・孫数を示しています。国の将来推計を使って将来の子供の数を仮定していますので、それを使って孫数などを出している。その子供の世代、2000年生まれ、右下です、現在24歳世代の最終的な子供の数の分布、孫数の分布が出ている。
これで注目していただきたいのは、一番極端な例として、孫のいない人の割合、青いバーです、数でいうと十数パーセントです。1970年世代でぐっと増えます、30パーセントを超えています。2000年代、現在の20歳代は、今の子供の産み方でいくと孫を持たない人が半分弱です。半分弱の人が、孫以降の子孫はいない、家系がそこで断絶するってことです。だから、人口減少っていうのは、結局、自分が子供を持つかどうか、孫を持つかどうか、ひ孫を持つかどうかという形に変えてみると、随分身近なものに感じられるわけです。50年、60年のうちには、今、日本にある家系の半分ぐらいは消えていくというようなイメージです。
そうしますと、将来世代に、子供、孫、子孫を残す人たちと、いやもう子供は持ちませんと、あるいは孫はいませんという人たちの間で分断が起きかねない。利害が対立する。つまり、将来の社会に対して現在払っている税金を使って投資を行う、未来社会への投資というものがあまり意味をなさない人たちが大量に出てくる。つまり、子孫はいませんという人たちです。
一方では、子供を育てるのは大変ですが、しかし同じ世代で子供を育ててない人が半分ぐらいいるとします。そうした場合に高齢になったとき、苦労して育てた子供たちが、子供を育てなかった人たちも含めて高齢者を支える。これ何かちょっと、子供を育てない人たちっていうのはフリーライディングじゃないのかといった不満が起きてくるのではないか。
最後、一つだけ申し上げたいのは、じゃあ一体どうしたらいいのかということですが、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、緩和策と適応策、両方やらなきゃ駄目だということなんです。少子化対策についてはちょっと今回そのお話できないので、ちょっと飛ばして。適応策のほうです。ここで重要なポイントを申し上げておきたいと思います。
適応策のほうで申し上げますと、資料60ページですけれど、これは何かというと、上の表が高齢者は昔とは違うぞということを表しています。何が違うのか。健康度が違う。健康度ってどうやって表すのだと。いろんな表し方がありますが、一番確実といいますか、堅実なものは、平均余命というのがございます。
65歳であと平均何年、日本人は生きているかというのを正確に測定した数字がございます。この平均余命、これを65歳以上の人の健康度の指標として見ることができるであろうということで見ますと、1960年から、男性の65歳時平均余命が11.6年だったんです。これがどんどん延びているということは、65歳以上の健康度がどんどん上がっているということになるわけですよね。ということは、この健康度を高齢者の定義として活用するということができるようになります。
それはどういうことかというと、1960年に65歳時平均余命が11.6年の人が高齢者だったとすると、それと同じ健康度の人たちを高齢者として規定していくためには、平均余命が11.6年残っている年齢を高齢者の定義として使えばいい。それがこの表の真ん中の数字でございます。65歳から例えば2010年でいうと75歳ぐらいに増えています。10年増えている。健康度でいうと10年高齢者の定義を延ばさなきゃいけないってことになります。これは、男女それぞれ、将来的には80歳以上が同じぐらいの健康度になり、これが高齢者の定義になる。この高齢者の定義によって、例えば高齢化率を計算してみると、左下の紫のバーが暦年齢を使った場合の高齢者の割合ですが将来的に4割近くになっていく。しかし、健康度で定義すると割合がちょうど半分で済むということです。
先ほどの従属人口指数、人口ボーナス、人口オーナスの指標について見ますと、もっと大きな差がありまして、あまり従属人口指数、社会の負担が増えていかない。健康度を定義の基とした高齢化の定義を使いますと、何と人口ボーナスの状況を続けることが可能であると、こういうことになります。
これはどういうことかというと、特に高齢者が健康になっているということを生産性にそのまま結びつけることができれば、高度経済成長期の生産性を日本の社会は保てるということです。過去に比べて、そのぐらい日本の高齢者は健康になっています。さらに、資料62ページを見ると健康だけではなく、教育程度もどんどん上がっている。つまり何が言いたいかというと、現在の高齢者、そしてさらに将来の高齢者は、健康度も高い、教育程度も高い、人口の質が高い、どんどん高くなっていき、生産性がどんどん高くなっていくということを数字は示しています。ただし、問題は今の制度ではそれが生かされていないことです。
ですから、もし高齢者が健康になっている、まだ生産性をたくさん保っているのに、過去の制度によって引退してしまったら、当然、生産性が無駄になるわけです。だから、そういった健康度とか教育の質が高まっていることを生産性に結びつけるような仕組みに変えていくことができれば、高齢化社会は決して大変な社会、つらい社会ではない、暗い社会ではないってことです。高度経済成長期のような生産性すら保つことができるということであります。だから、今後の人口問題は、数や人口の割合、高齢者の割合を見るだけではなくて、人口の質の変化というものに目を向ける必要があるということです。
さらに進んでいえば、その質をより積極的に改善をしていく。つまり、健康になっていくというのをむしろ促進をする。教育程度が高まるということに関して、それを促進する。スキルアップにさらにそれを促進するような仕組みを作るということによって、人間の質、人口の質を高めることによって、人口の減少や高齢化というものには十分対処できるということが一応計算上は示すことができる。資料64ページにある課題への処方箋の基本的な考え方を示していますが、量から質というものに目を向けて、健康、教育、その他の人口の質を高めていくということがポイントになろうかということであります。
さらにいえば、いろいろ制約を受けている人たちの制約をなくすということが、生産性向上につながる。つまり、個人が能力を最大限に発揮するということをもうむしろ基本的な人権であるというぐらいに、社会が後押しをするような社会になれば、高齢化は乗り切っていける。逆にいうと、そういう社会にしなければ、高齢化は乗り切っていけない。さらには、そうした対象を格段に有効にするいろいろなイノベーションの活用ということが重要になると思います。
主な質疑
【委員】
既に昨年度で移民が341万人で、日本の全人口に対して約2パーセントを占めている。我が国では、難民が定着しているものと、専門的な知識を持つ外国人労働者を受け入れる政策移民の大きく分けて二つがある。そこで伺うが、人口に占める移民の割合は何パーセントぐらいであれば、適正の範囲内であると思うか。
【参考人】
直近の将来推計によると、今の状況が続くと2070年には外国人の割合は約11パーセントになるといわれている。これは、望ましいとかそういう形ではなく、今の状況が続くとそうなるという数字になる。11パーセントがヨーロッパでも見られる移民の割合に近いものになる。適正という言葉は難しいが、諸外国の例などを見ると、それぐらいの割合が個人的には適正ではないかと思う。
一方でこの課題は、国民的な議論をしなければならないことであるにもかかわらず、現在の段階では議論が進んでいない。まず議論するに当たっては、日本人とは何か、日本人はどうあるべきかを考えなければならない。労働力として受け入れられるものであれば、例えば人口比50パーセントぐらいまで入れてもよいではないかという考え方もある。これは、経済のことを考えると、それだけの幅があれば、労働力に余裕ができるという意味で、議論に値すると思う。そうすると、外国人が半分の社会というものとはどういうものかをいろいろな方面から議論しなければならない。
よって、むしろ適正な割合というのはこれから決めていく必要があると思う。
【委員】
次に、健康寿命と知的生産性について伺う。健康寿命について、資料60ページは男女を含めた数でよいか。
【参考人】
これは、男女別で表を分けている。ただし、もともと女性のほうが同じ65歳でも長生きなので、将来的に1960年基準65歳等価年齢は男性が79.3歳、女性が80.8歳となる。これが1960年の65歳の人と同じ健康度になる年齢である。
【委員】
健康度による高齢定義において、女性は健康寿命の統計値とおおよそ合致しており、男性の健康度をもう少し上げていかなければならないと考えればよいか。71歳からが高齢者であるため、この場合、高齢者の基準を77歳、78歳になるべきだということで定義すると、基準年齢をもう少し上げていかなければならないのか。
【参考人】
この数字は、国の将来推計人口、今の社会の変化が続くとするとこうなるであろうという寿命の延びを示したものである。よって、これをより促進していくのであれば、より健康度が高まり生産性は高まる。
【委員】
次に、人口減少社会においては二つの大きな課題があると考えており、一つ目が移民の問題で2070年には移民の人口に占める割合が外国と同じようになること。二つ目が、我々がもう少し年を取っても、しっかりと働ける知的生産性の高い人たちが残るとされているがなかなかそうもいかない部分があることである。そうしたときに、フリーライドの防止を整備したうえで、移民の割合を11パーセントから上げなければならない。
今でも生活保護費について、最高裁判例が否定したとしても、保護を一義的にやっており、最も大事な部分が欠落したまま議論が進んでいる。そのあたりどうなのか伺う。
【参考人】
なかなかそこは難しい問題である。まず、人口学の立場からいうと、日本側でいくら外国人労働者を受け入れたいと思っていても、これまで受け入れてきた中国や東南アジアの国々がどんどん高齢化していくので、若い労働力はそういったところでも必要とされ、なかなか外国に出すことは難しくなる。また、経済的な賃金格差があって初めて外国人の労働者は来てくれるが、日本の賃金は今難しい状況であり、今後どうなるか分からない。そのように幾つかの考慮すべき要素があり、どれくらいを目指すべきかは、また別途議論すべきことだが、人口学の立場からいうと、今後、早急に移民を増やしていくことは難しいのではないかと思う。
何にしろ、外国人を受け入れることに関して、各分野からの議論がまだ全然足りない。特に愛知県は外国人がたくさん入ってきており、そのことについては、一番先端地域だと思うので、大いに議論していくことがまずは大切である。議論が深まっていない中で、見切り発車してしまうと、後から大きな損失となる可能性がある。
【委員】
少子化には構造上の問題もあると先ほどの意見陳述にあったため、それに関連して質問する。
まず移民について、現在の日本の人口の年齢分布として、生産年齢人口の減少が一つ大きな現状、プラス課題としてある。生産年齢人口を純粋に増やしていく形の一つが移民であると思う。
今、愛知県の人口は750万人で、その内外国人が29万人ぐらい愛知県にいる。割合にすると、おおよそ4パーセントぐらいだと思う。ヨーロッパ諸国のように、人口比11パーセントとなると人数が2倍から3倍ぐらいになるイメージだと思っている。移民は生産年齢として一時的に増えるかもしれないが、長い目で見て、外国人が移民として増えることで、本当に生産年齢が増えるのか疑問である。
移民は、緩和策であって、解決策ではないと思うが、構造上の課題を解決できるものなのか改めて伺う。
【参考人】
日本の場合、政府は移民という言葉を使っておらず、外国人としている。今の質問でいうところの外国人労働者になるが、外国人労働者は一定の期間、日本に来てもらって、最終的には自国に戻ってもらうことを前提に来てもらうものである。当然、若い働き盛りのときに来てもらい、滞在年限を迎えた段階で通常は帰ってもらう形になる。現在、家族の帯同といった条件等がいろいろと議論されているが、基本的には一時的に来てもらう考え方が、現在の考え方である。
移民と考えた場合には、必ずしもそういう年限を決めず、日本国民として来てもらう形になる。そうなると、今度は高齢者になったときの社会保障等を日本人と同等にしていかなくてはならない。そうすると、また新たな今までにない考え方、仕組みを運用していくことになる。
移民として、新しい国民として受け入れるという、ヨーロッパの国々がしているような形にしていけるのか。それとも、一時的な外国人労働者として滞在をしてもらう形にしていくのかという、基本的な考え方についてまだ世論が定まっていないと思う。そういう根本的なことを明らかにした上で今のことも考えれば、どういう形で受け入れるかも決まってくる。
【委員】
次に、高齢者の定義を変えていき、生産性を高めていくことも経済活動の面では一理あると思う。しかし、人口の構造上の問題は、何も解決されていないと思う。高齢だから駄目だといっているわけではなく、例えば高齢出産の定義を変えたとしても、そのことによって体への負担が減るものではない。先ほどの意見陳述での人口ボーナス、人口オーナスについても自分の中ではしっくりとこなかった。
そこで、定義を変えていくことによって人口の構造上の問題が緩和できる根拠等を改めて伺う。
【参考人】
資料60ページの表とグラフで示しているものは、国の将来推計を基にすると、今後、社会が進んでいき健康度がさらに改善をしていくことが見込まれており、それを使って高齢者の定義を変えてみる、つまり健康度によって再定義をしていくと、高齢化の将来像というものが大きく変わってくるものである。つまり、現在の仕組みでは、多くの生産性を持ったままそれが生かされない形で推移をしていく。この紫色のグラフと水色のグラフが、その差ということになる。そして、この水色のグラフ、右側のグラフを見る限りでいうと、人口ボーナス、高度経済成長期の生産性、かつて日本国民が持っていた生産性と同じレベルの生産性を、高齢者が健康になっていることを生産性に結びつければ保つことができるというものである。ただし、これは制度を変えないと駄目である。今のままでは紫色のグラフになっていく。
それと、年々高齢者の教育水準が高まっていることを生産性として捉えて、それを生かし、いろいろな制約のある層に関しても制約を取っ払って、国民が持っている能力が最大限に発揮できるような形にすることができれば、恐らく人口ボーナスのとき以上の生産性を確保することができる。さらに、資料64ページの(3)社会イノベーションの実現に書いてあるが、いろいろな技術革新である。
例えば、コロナ禍の中でリモートワークが一般化し、例えばプログラマーであれば通勤せず自宅で作業しても全く支障がない職種となった。そういった、新たな技術的なイノベーションによって、さらに健康になっている、あるいは弱っていく部分を補助するような技術あるいは社会技術と呼ばれるような、社会インフラを変えていくことも重ねて行っていけば、さらに高度な生産性を保つことができる。ただし、今のままでは駄目だということである。
【委員】
参考人の話を聞き、非常に危機感を実感した。政治や世の中の議論の視座が低過ぎるというか、本質を全く捉えられていないと感じる。
理由は二つある。一つは、政治との親和性は難しいのではないかと話があったが。端的にいうと、これは立法不作為だと思っている。それは何かというと戦後レジームである。優生保護法、今は名前を変えて母体保護法になっているが、その法で定める中絶の条件として第14条第1項第1号で「妊娠の継続又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」としており、出生数が80万人を切る中、経済的な事由により人工妊娠中絶で12万の子供が亡くなっている。
人工妊娠中絶の是非を巡っては、他国であれば国論を二分している。しかし、日本に関しては、保守層の人からでさえもそういう声は聞こえてこない、母体保護法第14条第1項第1号の経済的な事由で人工妊娠中絶をする項目がある限り、指数関数的に日本の人口はどんな対策を打ってもゼロになっていく。子供をつくる行為はみんな大好きだが、出産、子育てになると負担を感じてその責任から逃げるみたいなことをやっている。要望に近い形になるが、こういった議論を、人口戦略会議や学会で活発化させてもらいたいと思うがどうか。
【参考人】
人工妊娠中絶の問題は、世界でもいろいろと議論がされている。
もちろん日本でも同様の議論があってしかるべきかと思うが、日本の場合を考えると、人工妊娠中絶は多くの場合、望まない妊娠になる。つまり、出生を望まないにもかかわらず妊娠をしてしまったということであり、仮に人工妊娠中絶を禁止すると、望まない出生が実現することになる。それに対して生まれてきた後、どうすればよいか、極端にいえば、一生の社会保障をどうしていくのか、その後に問題を残さない形で対処ができるのかも議論しないと、将来に禍根が残ってしまう。
あまりいい例かどうか分からないが、かつてのルーマニアのチャウシェスク政権で、出生率が下がったときに、チャウシェスク大統領が思いつきで人工妊娠中絶をある日から突然禁止することを行った。その結果、当然、出生数は一時的に増えたが、その後、出生率はさらに下がっていった。
社会のほうではどういう問題が生じたかというと、子供が捨てられ、ストリートチルドレンになってしまう事例が多く発生した。その子供たちが集まりギャング組織になったりした。人口に関する施策はいろいろなところに波及していく。そのため、いろいろなことを勘案した上で、実施しないと大きな問題につながっていくと思う。
【委員】
もちろん、暴行や脅迫による望まない妊娠に関しては、母体保護法の第14条第1項第2号に規定があり、これは必要だと思う。問題なのは、第1号の経済的事由による中絶が12万件、コロナ禍前だったら14万件ぐらいある。このことは、日本特有で、優生保護法自体がナチスドイツもびっくりの優生思想に基づく法律であるため、これの流れをまだレジームとして残っていることが、人口減少の一つの原因だといっても過言ではないかと思う。
理由の二つ目が、政策上の瑕疵である。これは何かというと、超過死亡である。今回のコロナウイルスワクチンで、45万人以上の人が超過死亡している。震災や戦争がない限り、この超過死亡は発生しない。しかし、国立感染症研究所のデータなどを見ると、この3年間ぐらいで45万人の超過死亡が発生している。このことはもう厚労大臣も認めているが、厚労記者クラブで、その質問に対してはっきり答えにならない問題が生じている。統計学を駆使すれば原因はコロナワクチンだと分かる。
今回のコロナワクチンだけでなく、日本人は赤ちゃんの頃から大量のワクチンを打ち続けている。それが不妊症とかを引き起こしている見解も出てきている。少子化対策しなければならないといっておきながら、一方ではワクチン接種の大量虐殺をやっている。名古屋大学の名誉教授も、大量虐殺と公の場でいっている。そのため、これらのことも国で議論されるようになるとよいと思うが、参考人の見解を伺う。
【参考人】
コロナ禍における数年間、超過死亡が増えており、死因統計を見る限り、新型コロナウイルスの蔓延、感染拡大と老衰の関係で見ると、新型コロナウイルスによる死亡と老衰の増減と少し同調しているところがある。もともと死亡統計における死因に関して、超高齢になってくると死因の特定というのは極めて難しい部分が出てくる。そのため、そういった部分がかなり関係して超過死亡になっていると思われる。
指摘のあったワクチンに関しては、医学的な専門家による議論をしてもらわなければならず、統計だけでは分析は難しい。もちろん、あるときにワクチンを行って、その一定期間の後に死亡率がぐっと上がれば、ワクチンの接種と死亡の同調性があると統計に出てくるが、今のところ分析上、その傾向は見られないので、その辺はとにかく医学的な議論がまず必要ではないかと思う。
【委員】
医学的原因と統計学的原因を併せて調査していかなければと思う。しかし、学者も国の研究分野ばかりを補助金でやっている傾向がある。学術的なところだけに、原因究明を現状求められない部分があるため、ぜひそのことを公にしてもらいたい。
【委員】
移民問題と人口減少問題は、我々はこれから真剣に取り組んでいかないと大変な問題になると思う。先日、インドネシアへ行き、そこで、日本人がやっている職業訓練校を見てきた。訓練生は3,300人ぐらいおり、基本的な技術を教え込んで日本へ送り出すという機関であった。そこの日本人経営者が言っていた中で、一番印象に残ったのは、30年前は技能者として送り出して、自国に帰ってきても生かす道がなかった。ところが、現在ではインドネシアは経済力をつけてきたため、その技能を生かす道があるから3年か5年で日本から送り返してもらいたいといっていたことである。
日本の持つ技術を教え込んで習得させて、母国へ帰ったら、事業を起こすなり、いろいろな企業へ就職させることで、どんどんと生活が豊かになっていくため、外国へ労働者を送り出すことは、こういった使い道があると感じた。
また、このまま行くと日本は他国に雇い負けする。例えば、ベトナム人労働者も給与が高くなってきており、韓国では少子化がひどいため、技能実習生でも日本の3割高い給与を支給している。
移民問題も、これからは単なる単純労働ではなく、質の高い労働力が必要になる。外国人労働者へ、一定期間の技能教育や日本の慣習や文化を教えるべきだと思う。
先ほどの説明の中で社会のイノベーションについて触れていたが、これからは、元気な高齢者、女性、障害者をどうイノベーションによって社会へ労働力として送り出すかを考えることは本当に必要である。これらのことについて、参考人の見解を伺う。
【参考人】
技能実習生の件に関しては、国際競争という形でなく、諸外国と技術も含めた有機的なつながりを持って経済を発展させていかなければならない。そういう視点を外国人労働者、技能実習生の分野でも持つ必要がある。
現在、生産性を発揮することに制約のある高齢者、女性、障害者というものに目を向けて、社会参加、ある意味では社会包摂、労働力としての社会参加に対して、イノベーションをもって進めていくことが、高齢社会を進めていく上で重要なポイントである。
【委員】
高齢者、女性、障害者の層の人々を社会へ参加させることをどんどん進めていくべきだと思う。
また、これからAIの時代であり、うまく活用すれば、これらの人々も大いに社会で活躍できると思う。加えて、日本人として帰化する移民であれば受け入れてもよいと思っている。日本人として、人口オーナスも含めて負担をしてもらうことを、総合的に考えていかなければ人口減少社会を止められない。