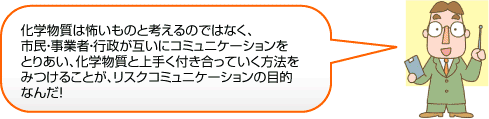本文
リスクコミュニケーションについて
化学物質による環境リスクをより小さくするためには、県民、事業者、行政が化学物質に関する情報を共有し、意見交換を通じて意思疎通を図り、相互理解を深めることが必要です。
これをリスクコミュニケーションと呼んでいます。
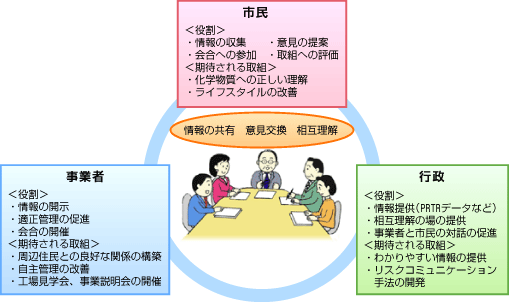
県民の皆様へ
私たちの生活には化学物質はかかせないものです。洗剤、化粧品、防虫剤、殺虫剤、塗料、接着剤、医薬品などたくさんの種類の化学物質に囲まれて生活しています。
自動車のガソリンやオイル、プラスチック製品、衣料品、電化製品、建材などの中に含まれ、意識せずに使っているものもあって、世界では約10万種類、国内では約5万種類もの化学物質が使用されているといわれています。化学物質なしでは今の便利で快適な暮らしは成り立たなくなっています。
しかし、その一方で、化学物質は日常生活のさまざまな場面を通じ、大気や水を経由して人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれがあります。
化学物質による環境汚染に関して安全で安心な社会を実現するには、県民、事業者、行政が情報を共有し、対話などを通じて、現時点における化学物質との最善のつきあい方をともに考えて、それぞれの立場で化学物質による汚染を減らすための取組を進めていく必要があります。
リスクコミュニケーションでみられる誤解
- 化学物質は危険なものと、安全なものに二分される。
→体に必要な食塩でも、摂りすぎると毒になる。 - 化学物質の環境リスクはゼロにできる。
→完全にリスクをなくすことはできない。 - 化学物質の環境リスクについては、ほとんどの物質で解明されている。
→化学物質の種類が多く、有害性など不明な点も多い。
事業者の皆様へ
事業所の日常的な操業に関することや、化学物質による具体的な問題が生じた場合に、事業者と県民だけでなく行政も交えて情報を共有し、意見交換を行って相互理解を図っていくことが必要です。
- 事業所の環境への取組について知ってほしい
- 事業所の化学物質削減の取組が妥当かどうか、県民の意見を聞きたい
- 周辺住民から苦情が来るので、その原因と今後の対策について説明し、理解を得たい
リスクコミュニケーションでは、事業者や行政に対して市民が不信感を持っている場合があるため、回答の仕方を誤れば、「難しい言葉を並べてはぐらかされた感じ」、「きっと事業所に都合のいい情報を採用したんでしょう」といった住民の不信感を生み出す可能性があります。これでは、せっかくの機会を台無しにしてしまいます。
そこで必要になってくるのが、中立的な立場から議論を整理するファシリテーター(司会進行役)や、中立的に分かりやすく情報提供できる化学物質アドバイザー(解説役)です。
リスクコミュニケーションのお手伝いをします
愛知県では、リスクコミュニケーションの開催を希望する事業者の方に、リスクコミュニケーション開催に当たってのアドバイスの提供や、当日の職員参加などのお手伝いをします。
- リスクコミュニケーション開催にあたってのアドバイス
- ファシリテーター、化学物質アドバイザーについての相談
- 当日の職員参加 など
お気軽に御相談ください。